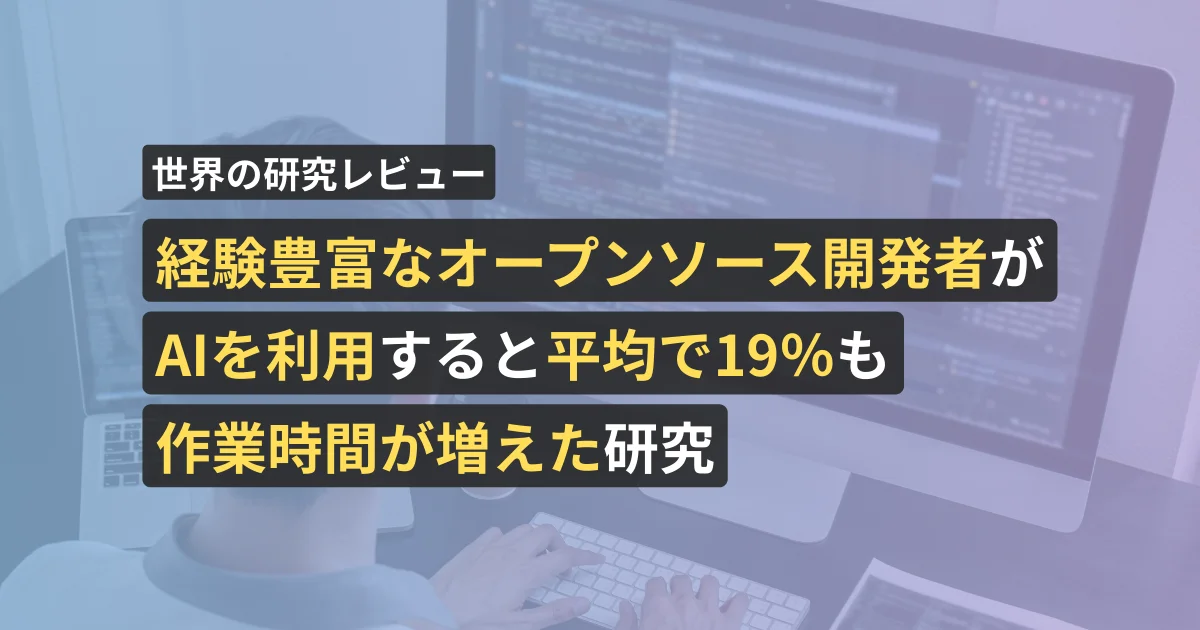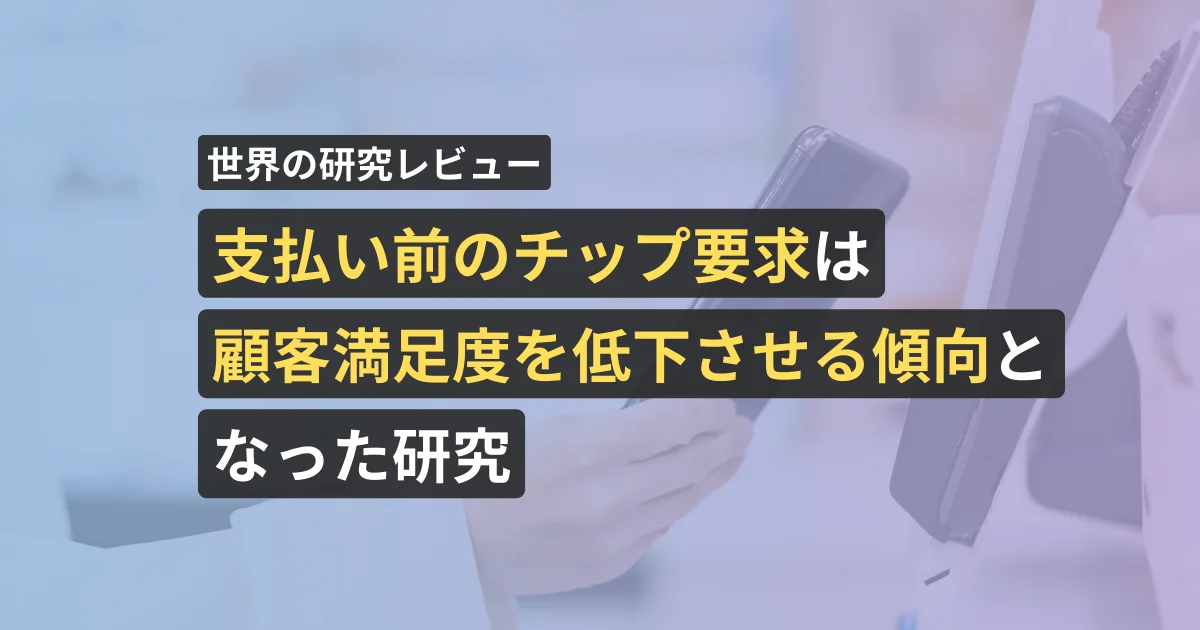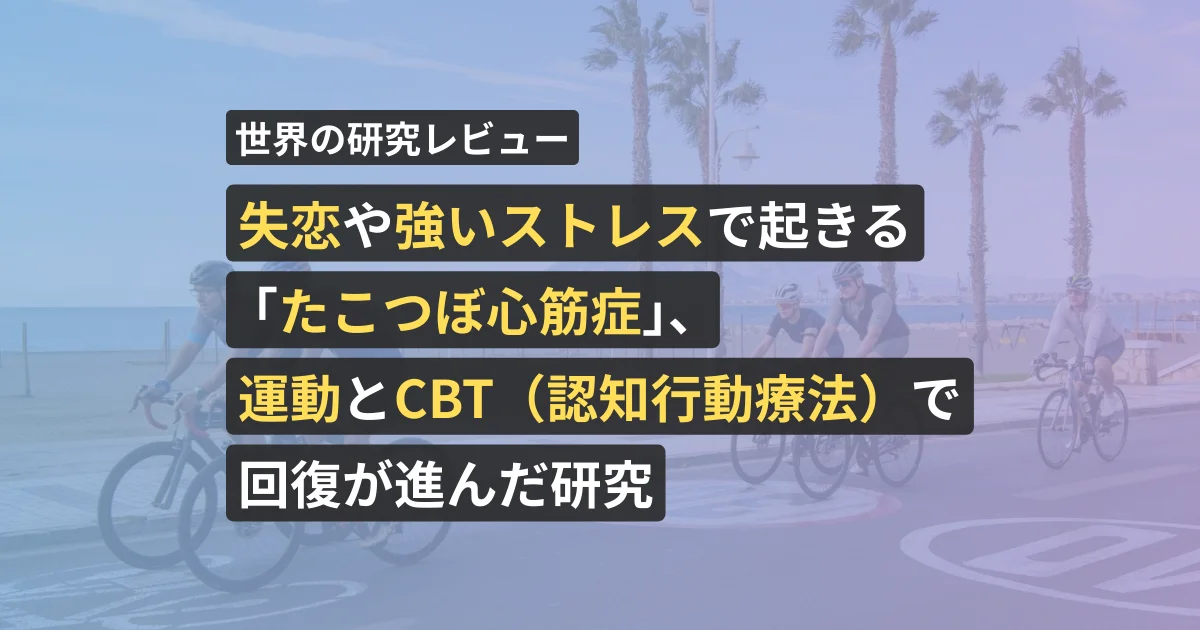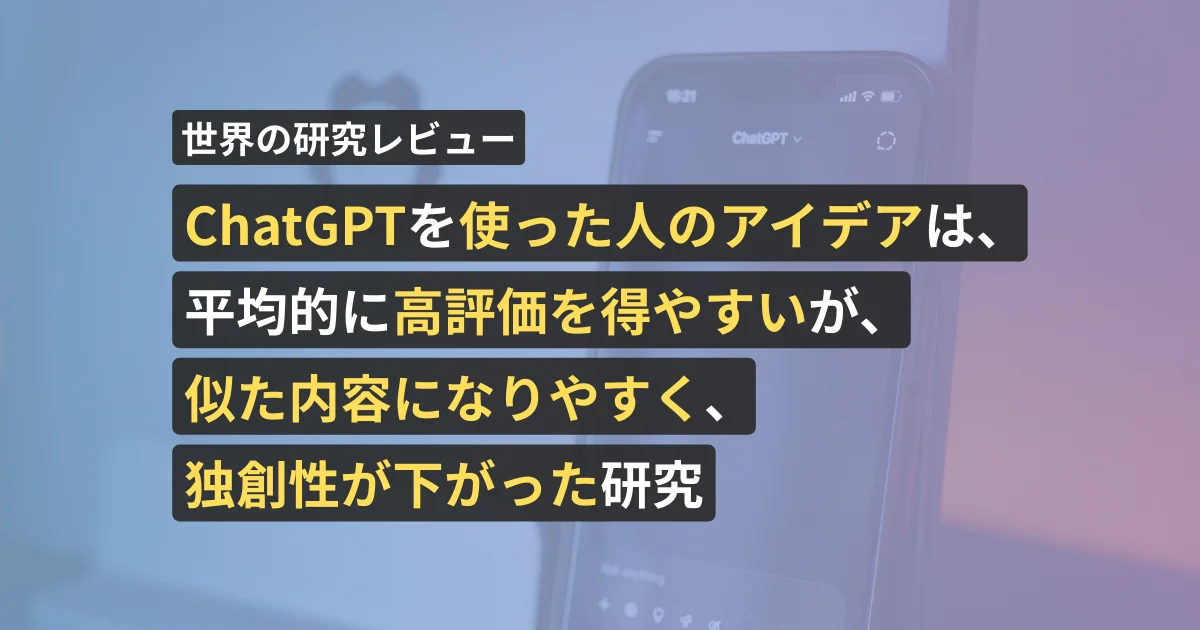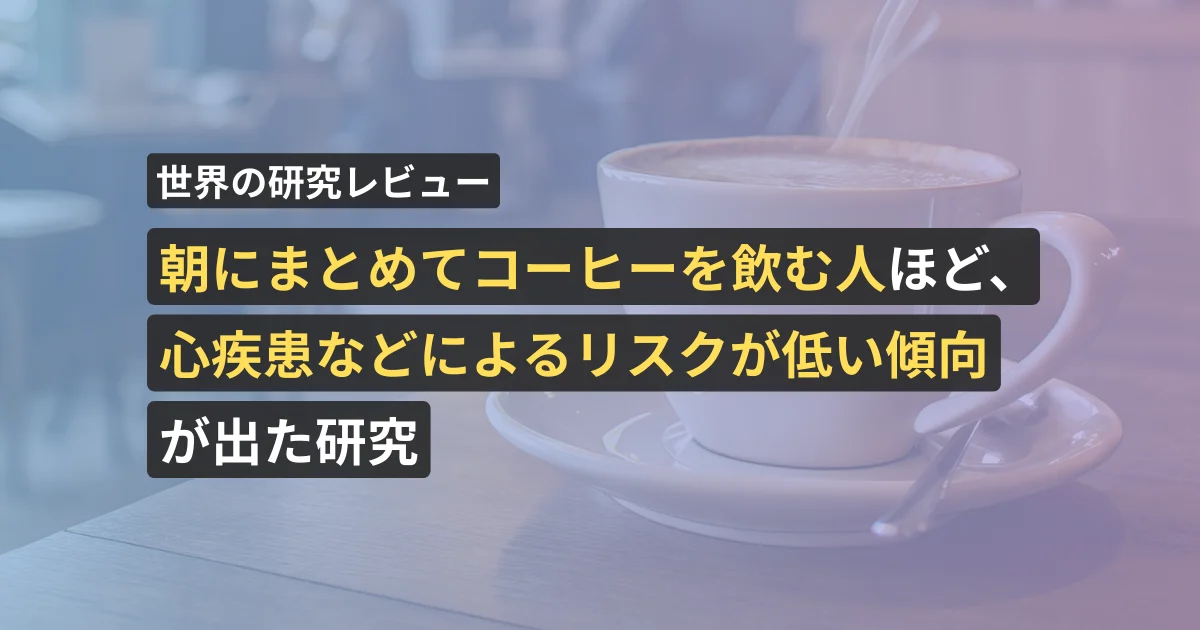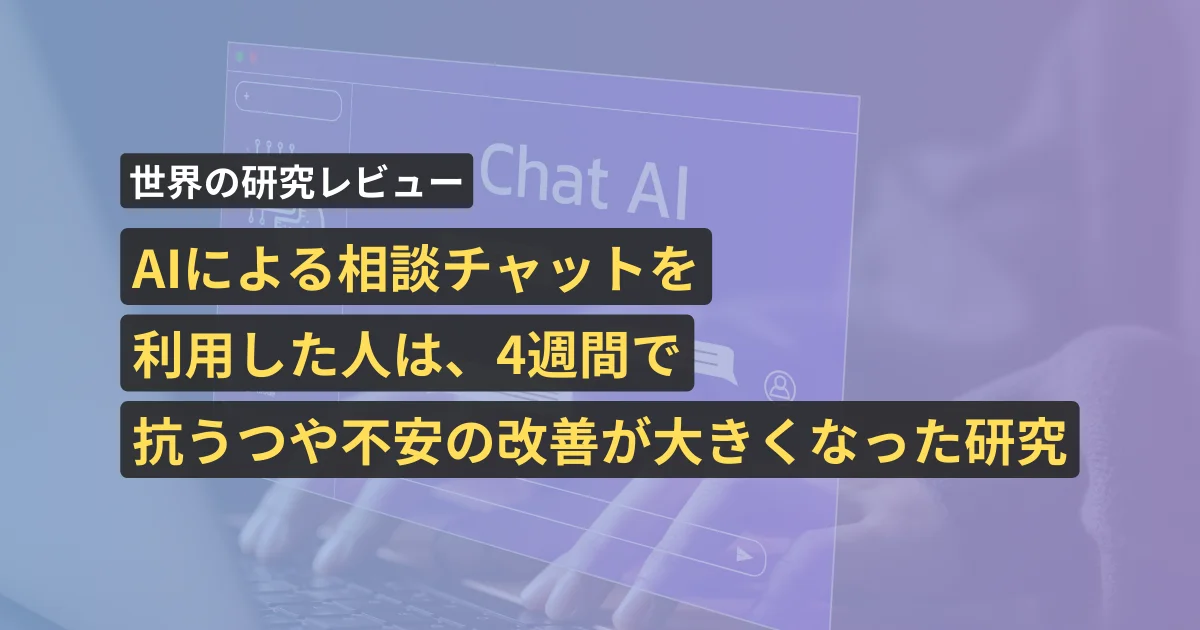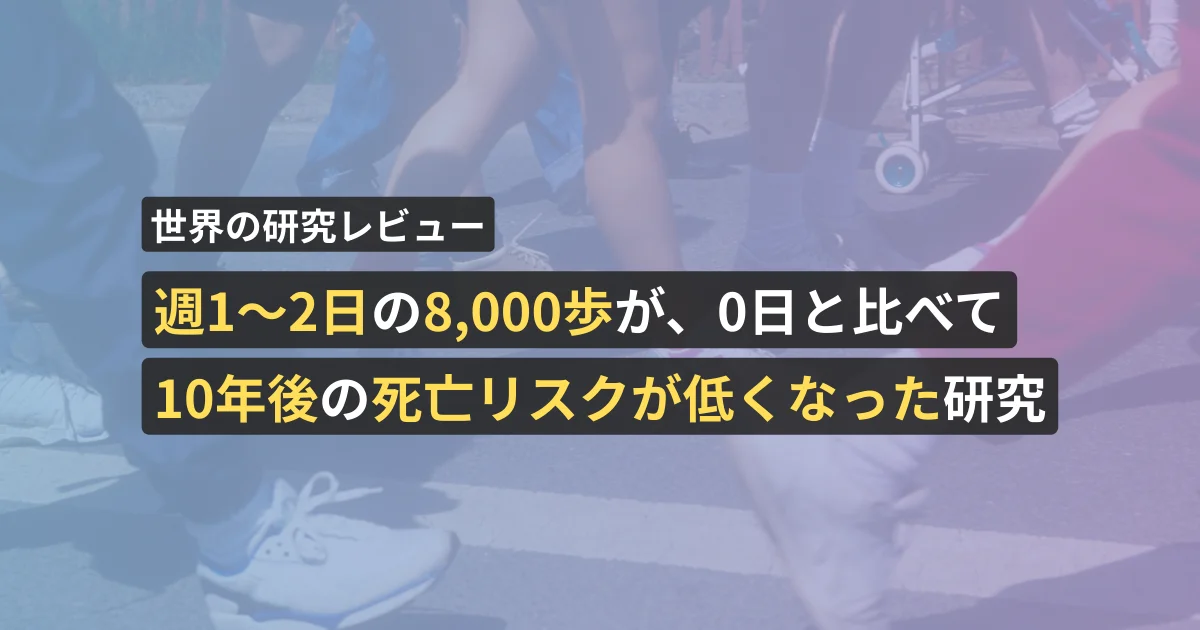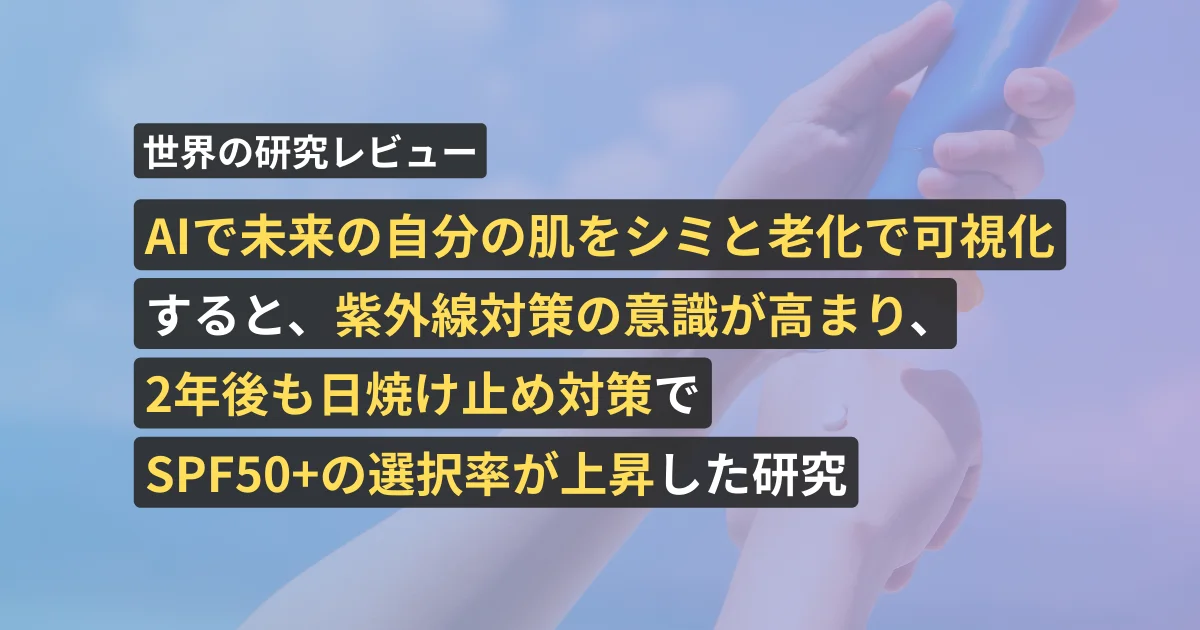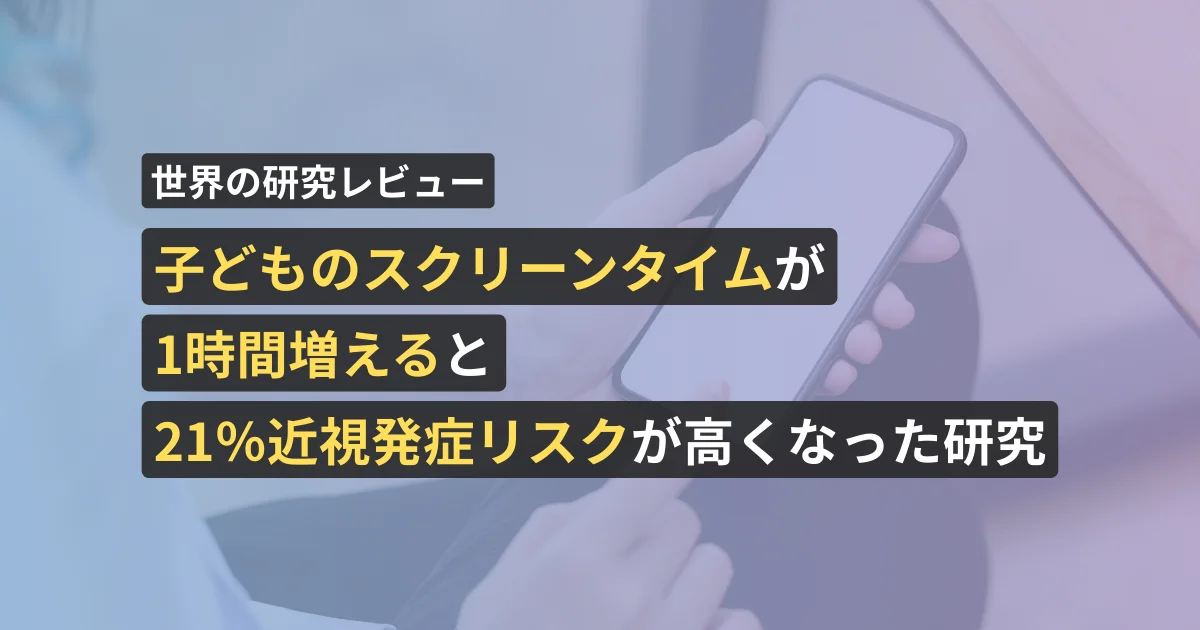「AIを使えばコーディングは一気に速くなる!」そんな期待が広がっています。
しかし、米国の非営利研究機関METRが2025年に実施した大規模実験では、経験豊富なオープンソース開発者がAIを利用すると平均で19%も作業時間が増えるという結果が報告されました。
この記事では、METRの研究内容を詳しく紹介するとともに、AIを効率的に活用するためのヒントを解説します。
- METR研究ブログ「Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity」
- arXiv論文「Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity」
本研究の要点は以下の通りです。
- 経験豊富なオープンソース開発者16人が実課題246件に取り組んだランダム化試験で、AI利用可のタスクは平均+19%の時間超過となった
- 参加者や有識者の多くは「AIで速くなる」と予想していたが、現実は逆の結果だった
- 大規模コードや文脈の多い課題では、AIの出力を理解・調整する「下ごしらえ」に時間を取られる傾向がある
- 生成結果の採用率が高くなく、レビューや修正に余分な時間がかかる
- モデルが暗黙知やプロジェクト固有のスタイルを把握しにくい
- 「AIなら速いはず」という先入観から試行錯誤が増える
- 用途を絞る:雛形作成、コメント生成、テストコード作成などに限定する
- 受け入れ基準を先に定義:AIの提案はその基準で速やかに取捨選択する
- 提案を丸のみしない:差分レビューやローカル実行で早めに検証する
なお、本記事の内容については、表現に不自然な点がないか、医学雑誌の編集にも携わっていた編集の専門家が確認済みです。
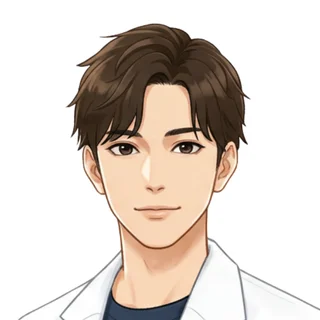 Touma
Touma編集プロダクションでの勤務経験があり、医療系出版社の月刊誌にて校正、校閲業務実績がございます。
おすすめ記事
研究の概要
今回の研究は、実際のリポジトリを用いて、AIを使った方が本当に開発作業が速くなるのかを検証したものです。特徴的なのは、単純なアルゴリズム課題ではなく、Linuxカーネルなどの実務に近い条件でタスクを評価した点です。
経験豊富なオープンソース開発者16人が、246件の課題に対してランダムに「AI利用可/不可」の条件で取り組み、作業時間やコード品質などが詳細に計測されました。
- リポジトリ:ソフトウェアのプログラムや関連データをまとめて保管・管理する場所
- Linuxカーネル:コンピュータの基本的な動きを管理するソフトウェアの中核部分
| いつ | 2025年1月29日 |
|---|---|
| 誰が | オープンソース開発に精通した熟練エンジニア16人 |
| 対象 | 各参加者が関わる大規模リポジトリの中から抽出された、Linuxカーネルを含む計246件の実際の課題 |
| 何をしたか | 課題ごとに、AI使用「可」または「不可」をランダムに割り付け |
| 方法 | Cursor Pro上でClaude 3.5/3.7などを使用 |
| 結果 | AI使用可の課題では、完了時間が平均で19%長くなることが確認された |
| 予想との ズレ | ・事前には平均で24%の時間短縮を期待していたが、実際は逆効果 ・事後の自己評価でも、参加者は20%程度の短縮を見込んでいた |
| 周辺所見 | AI出力を実際に採用したのは一部にとどまり、レビューや不要な修正・掃除に時間を割く傾向が見られた |
なぜAIで遅くなったのか
実務の課題は規模が大きく、プロジェクトの歴史やコーディングの流儀も含めた複雑さがあります。AIはコード片の提案には優れていますが、プロジェクト特有の前提や暗黙知まで正確に理解するのは難しい場合があります。
その結果、生成されたコードのチェックや修正、追加テストの作成などに多くの時間が割かれ、作業がかえって遅くなるケースが生まれました。METRの研究表では、「AIの信頼性が低い」「暗黙知の活用が難しい」といった要因が、遅くなる側の理由として挙げられています。
さらに、参加者は熟練開発者であっても、CursorなどのAIツールの使い込みは半数以下にとどまっており、道具への熟練度の差も作業時間に影響した可能性があります。
どう使えばプラスにできるか
AIを効率的に活用するには、まず役割を小さく限定して始めるのが良いでしょう。例えば、雛形作り、ドキュメントの下書き、テストケースの雛形作成、リファクタリング候補の列挙など、仮にAIが外しても致命的でない作業から入るのがおすすめです。
次に、作業前に「受け入れ条件」を短く書くことが重要です。AIの出力を条件に照らして素早く合否判定し、使えない案は即座に却下します。これらの手順を決めておくことで、不要な試行錯誤に時間を取られにくくなります。
レビューの流れを固定すると効率が上がります。具体的には、
- 差分レビュー
- ローカルでの実行
- 最小再現のテスト追加
という順序で確認するだけで、試行錯誤の迷子時間を大幅に減らせます。
システム開発におけるAI活用に関するよくある質問
まとめ
今回のMETRのランダム化試験から学べるのは、「AIを使えば必ず速くなる」と決めつけてはいけないという点です。経験豊富なオープンソース開発者でも、AIが生成したコードの見直しや手直しに時間を取られる場面が多く、平均で19%の作業時間増加が観測されました。
この実験は、Linuxカーネルなどの実務に近い課題で行われたため、現場でのボトルネックを浮き彫りにしています。したがって、AIを活用する際はタスクを小さく切り出して役割を限定し、まず検証することが重要です。
こうした設計を意識することで、初めてAIによる効率化や加速が現実的に期待できるでしょう。
おすすめ記事