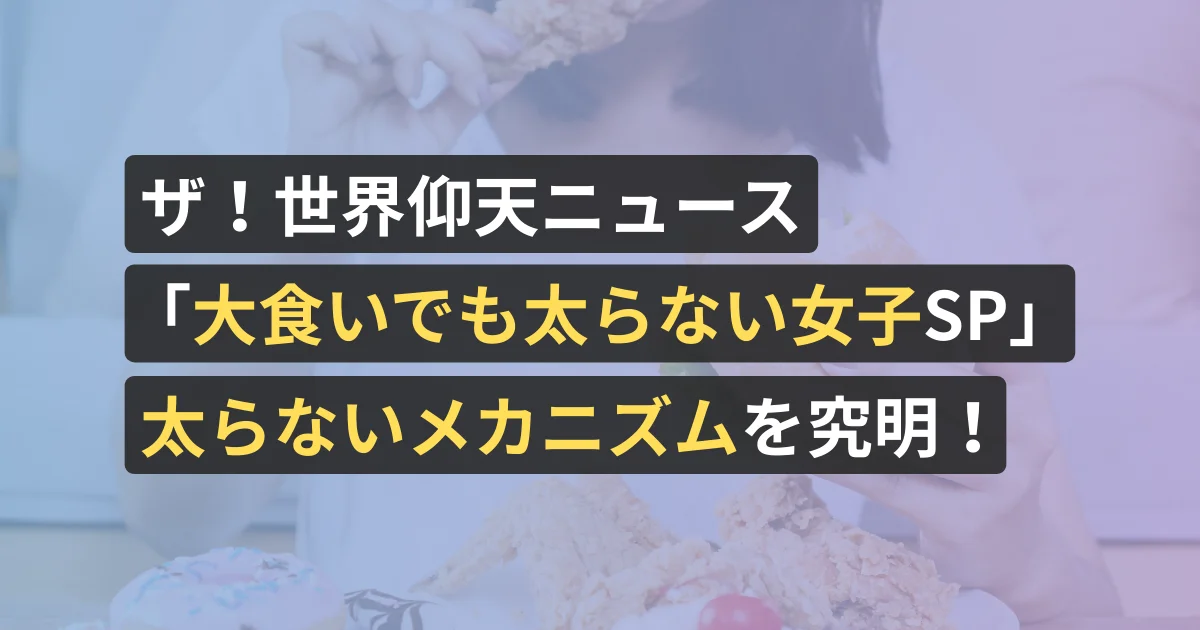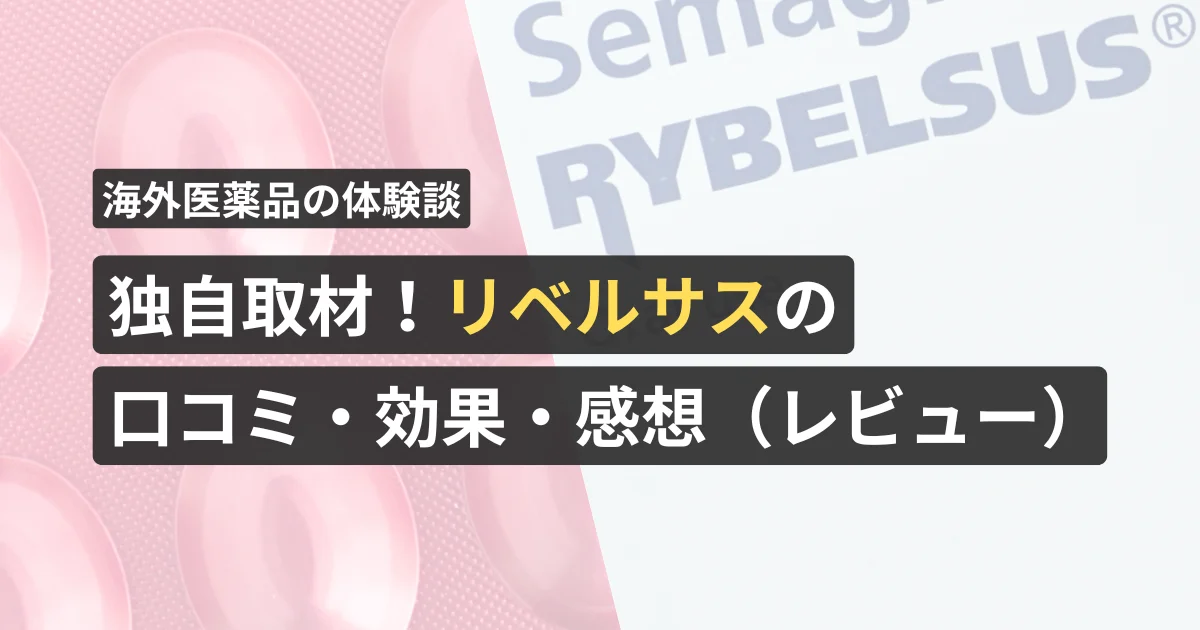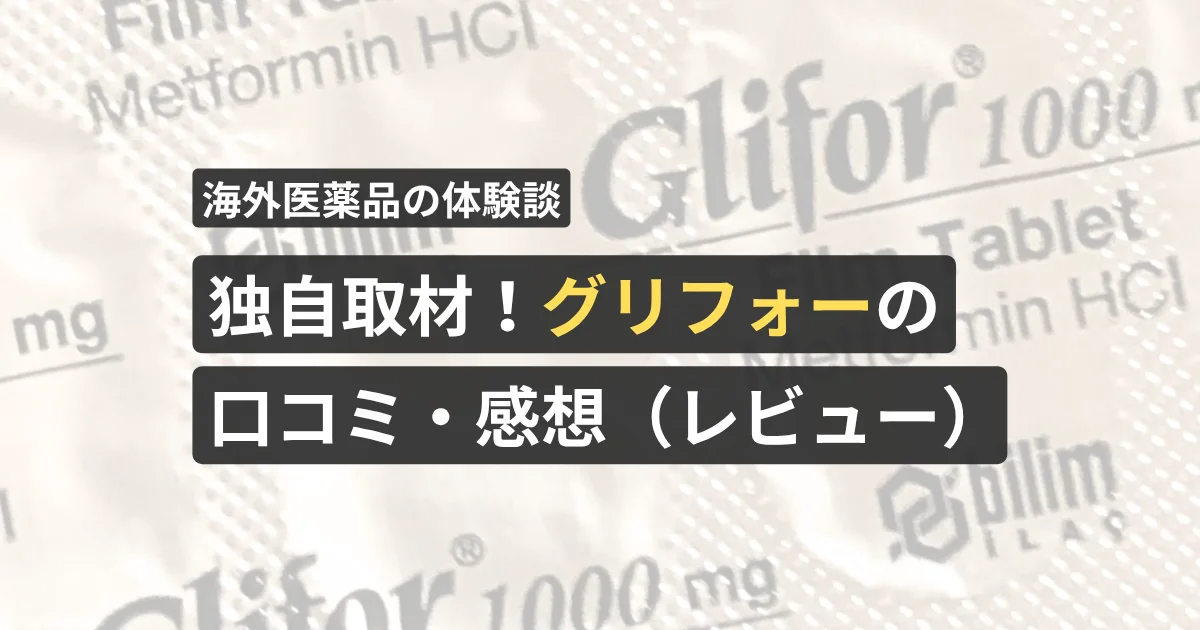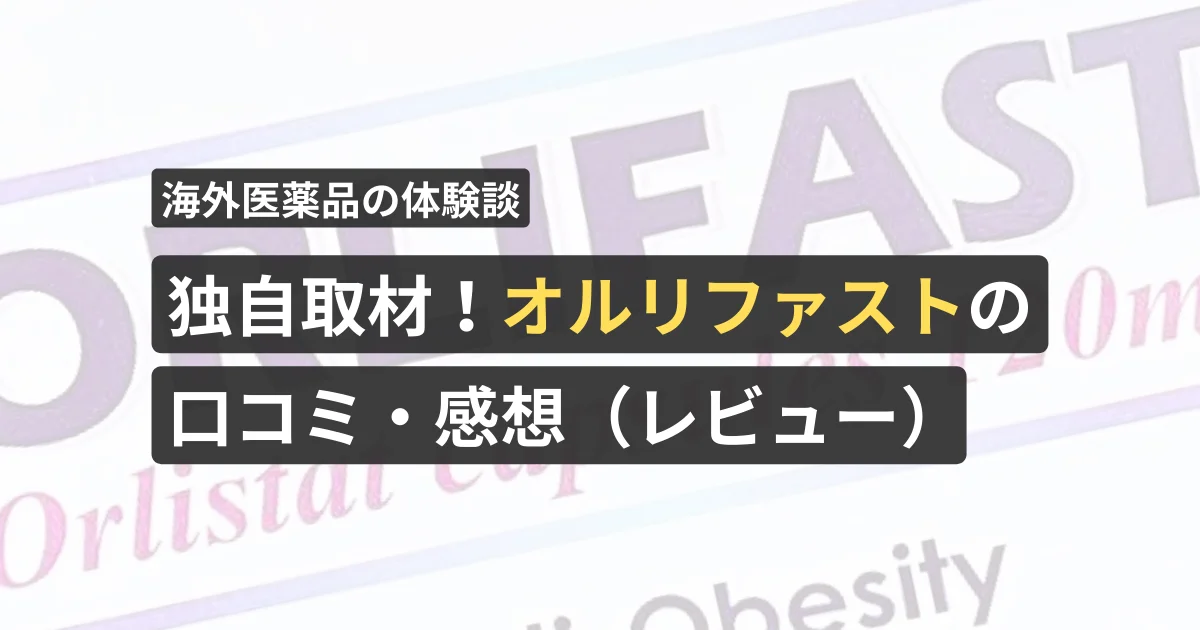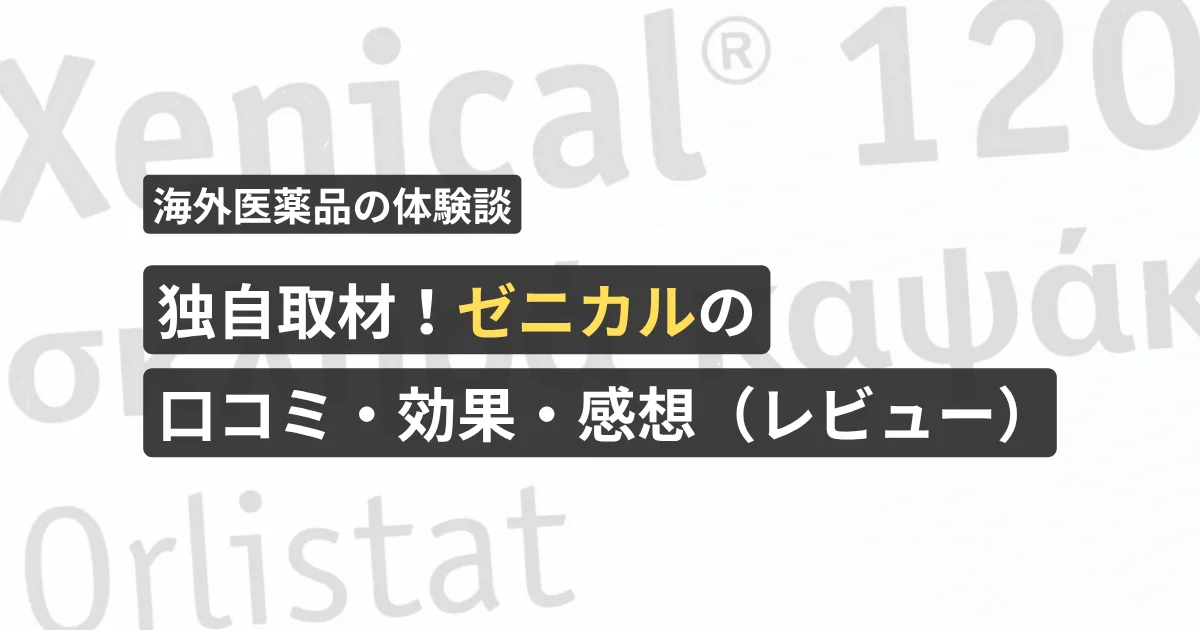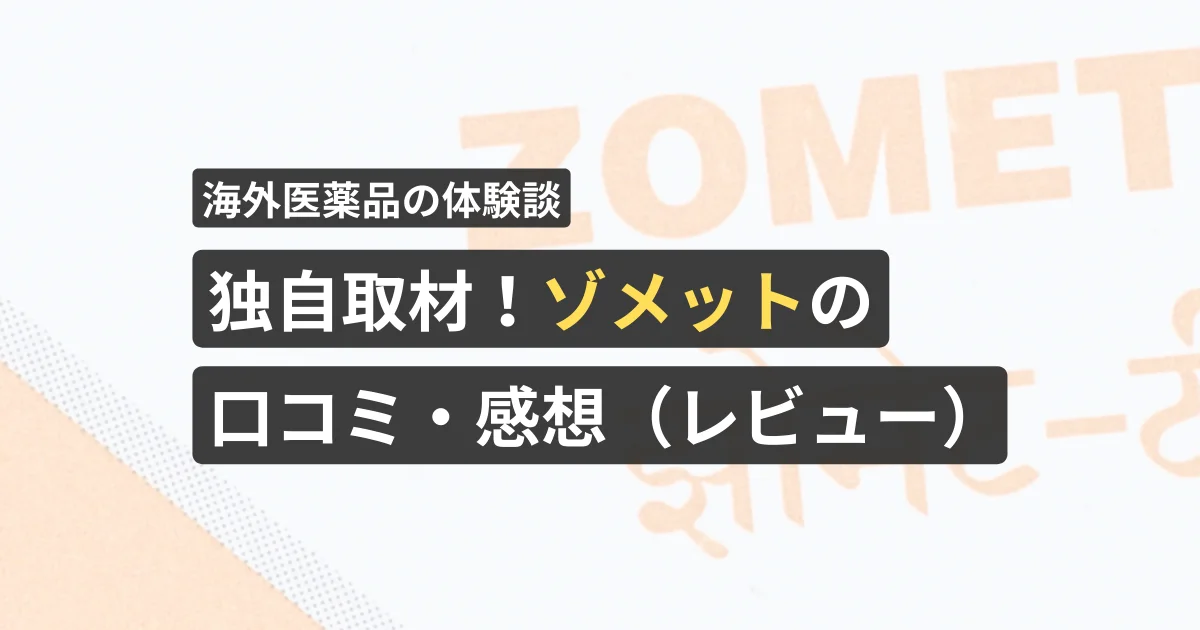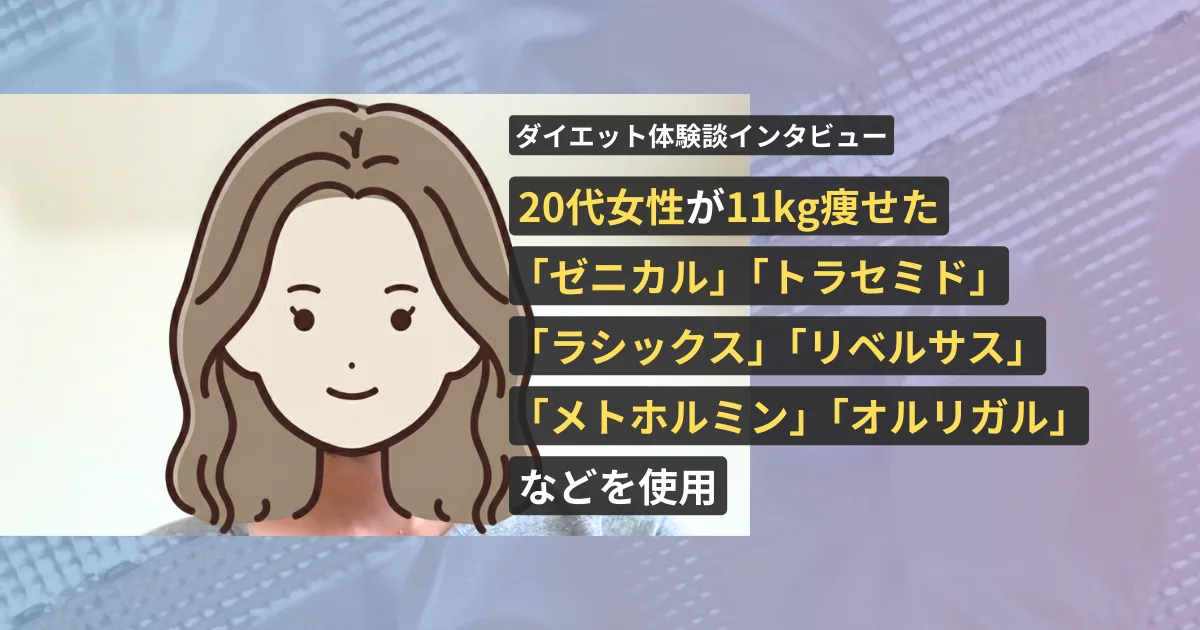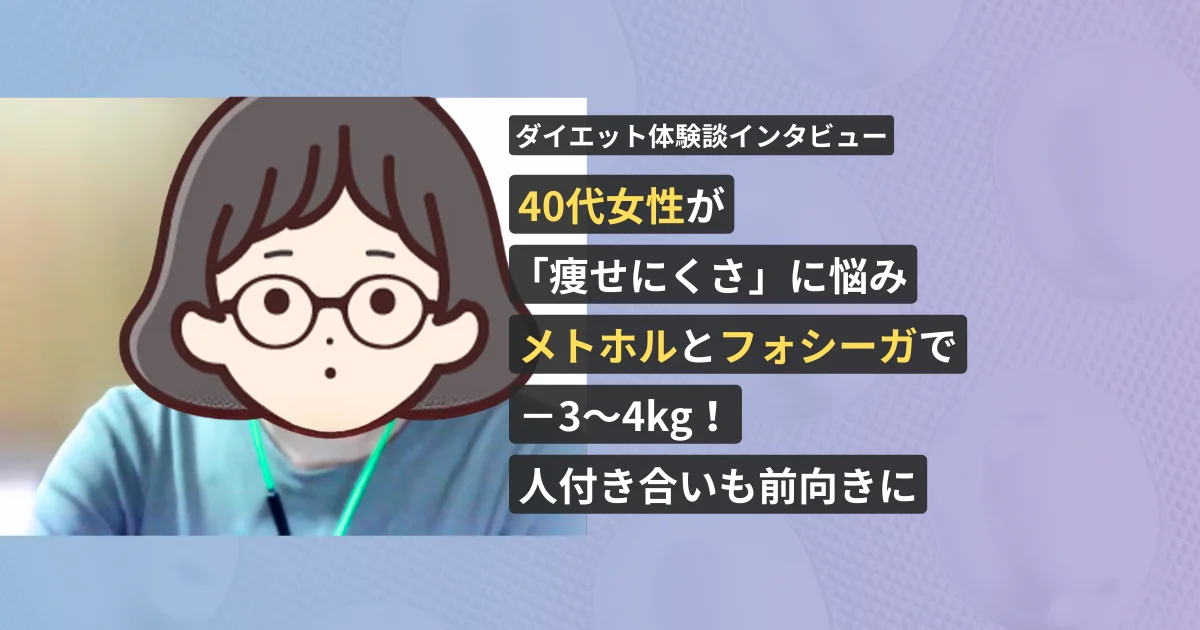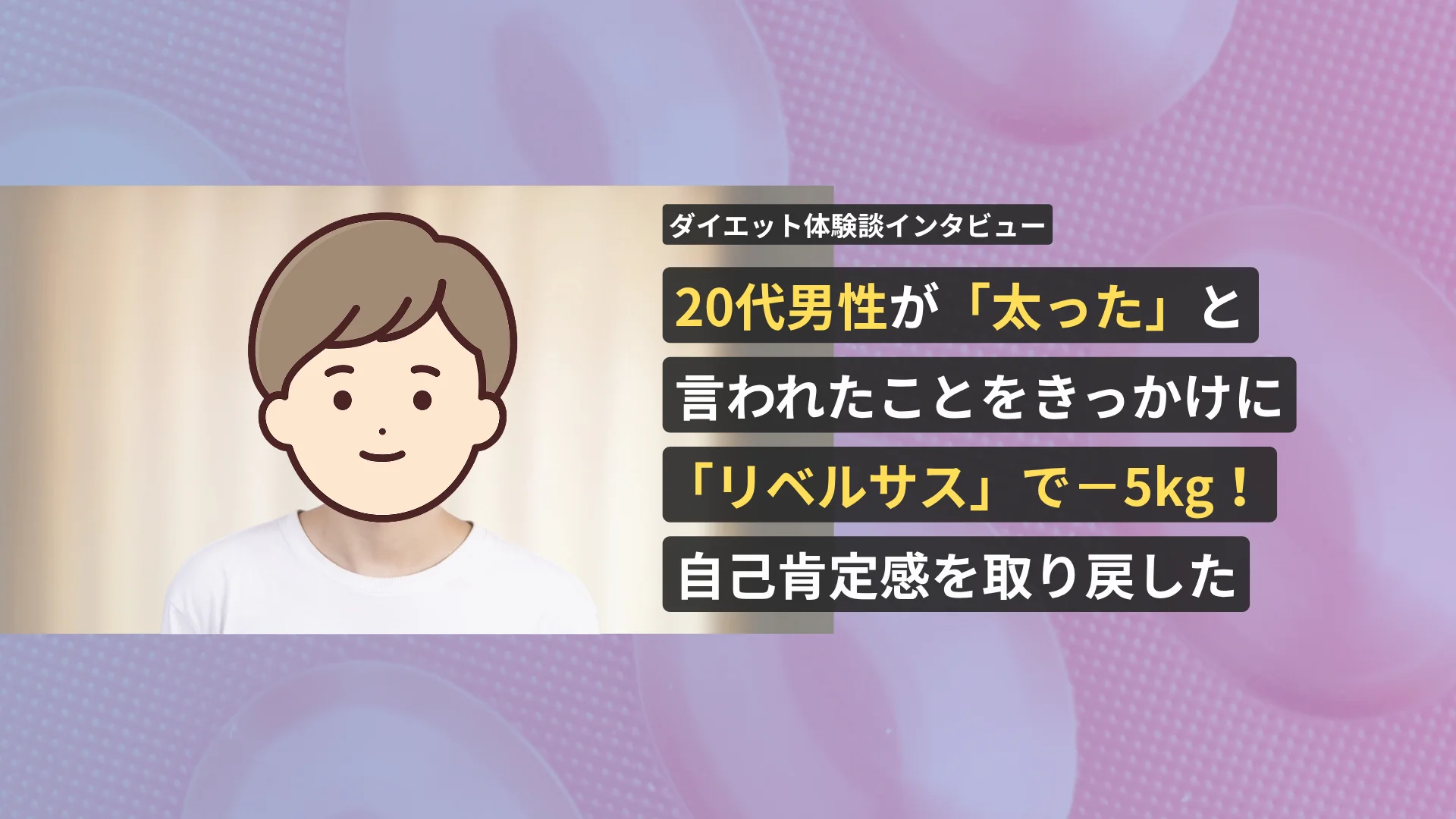大食いを特集したテレビなどでたくさん食べているのに全然太らない女性を見かけたことはありませんか?ちょっと食べるだけで体重が増えてしまう人からすると、うらやましい限りです。
2025年8月19日に放送された、ザ!世界仰天ニュース「大食いでも太らない女子SP」では超大食いなのにスマートな体型を維持している女性の日常を追い、太らないメカニズムを究明しています。
「大食いでも太らない女子SP」の要点は以下の通りです。
- ララさん:中学の運動部をきっかけに爆食いが開花し、数キロ単位の食事を完食できる体質に
- ちーさん:コロナ禍のストレスで食欲が爆発し、食べてもすぐ排泄されるため太らない
- 飯友らん子さん:家族ぐるみの大食い体質で育ち、腸内細菌の働きにより痩せ体型を維持
- 排便スピードが速い:通常より早く、食後6時間ほどで何度もトイレに行く
- 腸内フローラの違い:短鎖脂肪酸を作る菌や「やせ菌(バクテロイデスなど)」が多く、脂肪蓄積を抑制
- 遺伝や環境要因:母親からの体質や家庭環境の影響も大きい
- 胃腸への負担(胃運動不全、逆流性食道炎、裂傷リスク)
- 代謝や心臓への影響(血糖値上昇、脂肪肝リスク)
- 過食性障害やストレス起因の精神的リスクも潜む
なお、本記事の内容については、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
 Ray
Ray看護師資格を有し、総合病院で勤務。退職後、出版社に勤務し、医学誌の編集も担当しておりました。
おすすめ記事
ララさんの場合
身長155センチ・体重42キロのララさん。もともと彼女は、食事になんて全然関心のない少食女子だと思っていたのです。食べれば便秘もひどく、整腸剤に依存する日々が続いていました。痩せで大食いのお母さんは、体質は100%遺伝するものでもないと安心もしていたのです。
しかし、気づけば爆食いの遺伝子は、当たり前のように覚醒してしまったではありませんか。
ララさんは、中学生時代、陸上部に入部しました。ハードな朝練が続き、お腹が鳴るのが気になるようになって……。
その後、あれよあれよという間に、爆食いの遺伝子は堂々、開花してしまったのです。
昔の彼女は一体なんだったのかと思うほど、今は、5合の米 32匹のエビをのせた巨大エビ丼を完食。さらに、3キロのギョーザを19分の早食い。
遺伝、環境の全てが噛み合って生まれた大食い女子です。
卵かけご飯が変えた?
中学生になってララさんは、運動部に入って、いつもお腹がグーグーなってしまっていたのです。お腹がなるのがいやだから、無理やり食べるようになって。
しかし、お腹はぐーぐーなり続けたまま。
そこで卵かけご飯でするりとお腹に流し込む作戦に。そのとき彼女ははじめて、食べるおいしさに目覚めてしまったと言います。
ただし、普通であればあるはずのお腹一杯……という感覚がない。
MRIで胃の中を確認すれば
MRIで彼女の胃の中を食前と食後で見ると、食前は他の女性よりも小さいかなという感じだったのに、食後ではお腹の半分以上、胃が占めてしまっているではないですか。
医師いわく、遺伝的なものがあるとすれば、満腹に感じるリミッターがないか、高いことではないかということです。
ちーさんの場合
身長155センチ、体重40キロのちーさんも、小さい頃は少食少女だったのです。お膳スタイルで健康にいいものばかりが登場してきて、食事が全然楽しくなかったという記憶を持っていました。
彼女は、看護師を目指して大学に進学することになったのですが、コロナ禍でリモート授業ばかりの連続でした。
楽しいはずの大学生活が、誰とも話せないで外出もままならない状況にストレスがどんどん蓄積していきます。
このとき、お母さんが作り置きしていたカレーを食べて、彼女の爆食いの食欲が開花してしまったのです。
しかも、一杯食べたのにすぐに便で出て行ってしまうのです。
うどん10玉、冷麺12人前、5合分の巨大おにぎり、アイスクリーム2キロ、生クリーム1キロを完食。それは普段の当たり前のメニューです。
一体彼女の身体で一体何が起きてしまったのでしょうか。とても気になる問題です。
友だちと一緒に食事に行ったあと、友だちは、彼女のお腹だけでなく背中が張っているのを発見します。つまり、背中を圧迫する程までに胃が伸びているのです。
飯友らん子さんの場合
身長170センチ体重55キロの飯友らん子さんは、家族みんなが大食いで、小学生のときから給食はおかわりを繰り返し、隣りの教室の給食まで残飯を食べきる有名人と化してしまったのです。
現在の彼女は、昼食にバナナ24本と小玉スイカ1玉、夕食は寿司50貫とデザートをたいらげるのはごくごく当たり前。
彼女たちが爆食いしても太らない原因は何?
彼女たちに共通して言えるのは、排便のスピードが他の人たちより確実に早いことです。
普通の人たちであれば、1日以上たって排便モードに入るのですが、彼女たちの場合、6時間程度で、何回もトイレに行っているということが分かりました。
食べれば、お腹が出るのは当たり前のメカニズムなのですが、すぐに出てしまうから、お腹はすぐに戻ってしまうのです。
また、らん子さんの場合、短鎖脂肪酸を作る
- フシカテニバクター
- フィーカリバクテリウム
- ブラウティア
といった菌が何倍も多いことが分かりました。
短鎖脂肪酸は脂肪の蓄積を抑えたり、腸のぜん動運動を助け、排便を促す効果を期待することができます。



短鎖脂肪酸は、腸活の他にも肥満抑制、アレルギー予防、血糖値の調整、免疫力や持久力の向上など、数々の健康効果が研究により報告されています。
大食いのためだけではなく健康のためにもなくてはならないものです。
参考:
短鎖脂肪酸、注目の健康効果 – 短鎖脂肪酸とは|一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会
また、最新の研究では、やせている人たち、やせタイプの大食い女性の腸内フローラを調べれば、バクテロイデスという腸内細菌も明らかに多いという結果も出ています。
彼女たちの共通点は、大食いしたあとのトイレの回数は異常に多いことです。
それは、短鎖脂肪酸の効果によって健康な便がしっかり排出されているからであり、これにより太りにくいと考えることができます。
それ以外にもどうして爆食いをしても太らないのかは、胃の柔軟性・消化のスピード・基礎代謝など、さまざまな要因が絡むようです。
さらに注目すべきなのは、遺伝的要因です。
お母さんからの遺伝的傾向は、直接的な遺伝要因だけでなく胎内環境であったり家庭環境を通したりして子どもに影響します。
このような要因が複合的に作用し、大食いでも太りにくい体が生まれたのでしょう。



遺伝子は父と母それぞれから半分ずつ受け継ぐとされています。
そのため、お母さんが大食いで太りにくいからと言って必ずしも自分も大食いで太りにくくなるとは限りません。
参考:
個性ってなんだろう?- わたしたちの遺伝情報|一般社団法人 バイオインダストリー協会
そんな体質に意識的になれる?
そんな体質になりたいと思うものの「遺伝」ならば、どうしようもないと思ってしまうことでしょう。
しかし、ちょっとした努力で食べても太らない体にできることもあります。
たとえば、食生活を変え、腸内フローラを変えることです。
人間の消化管内は、だいたい1,000種類もの細菌が生息し、複雑な微生物の生態系を構築しています。これらが、びっしりと腸内に生息している様子を植物の群れにたとえられ、「腸内フローラ」(腸内細菌叢)と呼ばれます。
腸内フローラは、年齢や、食習慣、生活習慣の影響を受けて変化するため、ひとりひとり違っていることが明らかにされています。それぞれの菌がさまざまなな生理作用をもたらします。
ヤクルト中央研究所の行った研究結果によると、実際に腸内フローラを大人になって根本的に変えることには無理があるかもしれないけど、ある程度であれば変えられるということです。
腸内フローラを整えていくためには意識しなければならないのは食物繊維の摂取です。特に水溶性食物繊維を与えることが大事とされています。
さらに健康によい影響を与えてくれる活発な微生物(みそや、ヨーグルトなど発酵食品)を摂取すると、やせ菌は刺激を受け活性化されると言われています。



腸内フローラを整え、腸内環境をよくするためには食物繊維と発酵食品をバランスよく摂取することが重要です。
参考:
『食物繊維』×『発酵食品』で腸が若返る!|公益財団法人 宮崎県健康づくり協会(PDF)
ただし、専門家は番組内で「こうした真似は推奨せず、あくまで番組内の特異な事例として楽しむ」ようにと強調しています。
そのため、腸内フローラを整えることは良いですが、大食いは真似をしないようにしましょう。
太らない体質はこのままでも大丈夫?
一見健康的に見える痩せの大食いの女性たちですが、胃腸への負担がかかり、胃運動不全であったり、逆流性食道炎、裂傷のリスクもあります。
心臓や代謝への影響もあり、血糖値や脂肪肝のリスクが上昇すると言われています。過食性障害やストレスによる抑うつの可能性も出てくるでしょう。
羨ましがられる理由は充分にありますが、大食いでも太らない女子たちもさまざまな問題を抱えてしまいます。
もしも、自分も大食いだけど体形が変わらない、太らないという方は、一度消化器内科などの医療機関に相談することをおすすめします。
まとめ
大食いの女子たちが太らない理由は、短鎖脂肪酸を作る菌が多かったり、すぐに排便モードに入ることができたり、遺伝の要因もあるようです。
番組の中では、学生のころから際立った食欲、コロナ禍での食欲爆発、母子での共通体質などが紹介されていました。
ただし、長期的に見れば健康へのリスクも潜んでいます。この番組をキッカケとして食と体の仕組みについて、それぞれの方々が考えてみてはいかがでしょうか。
おすすめ記事