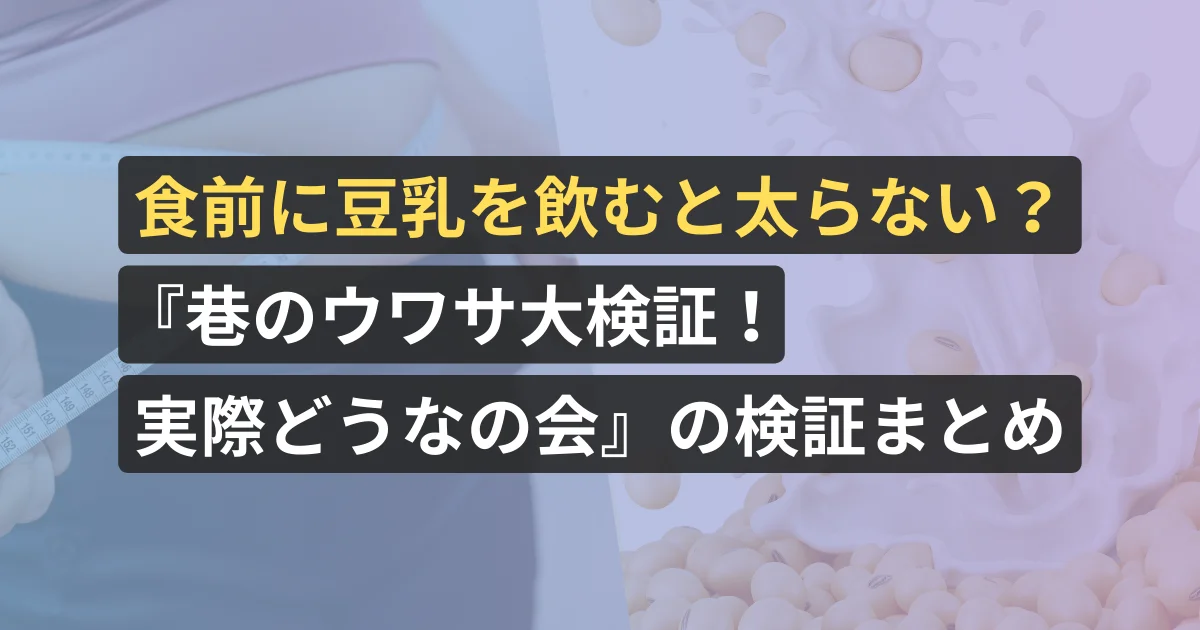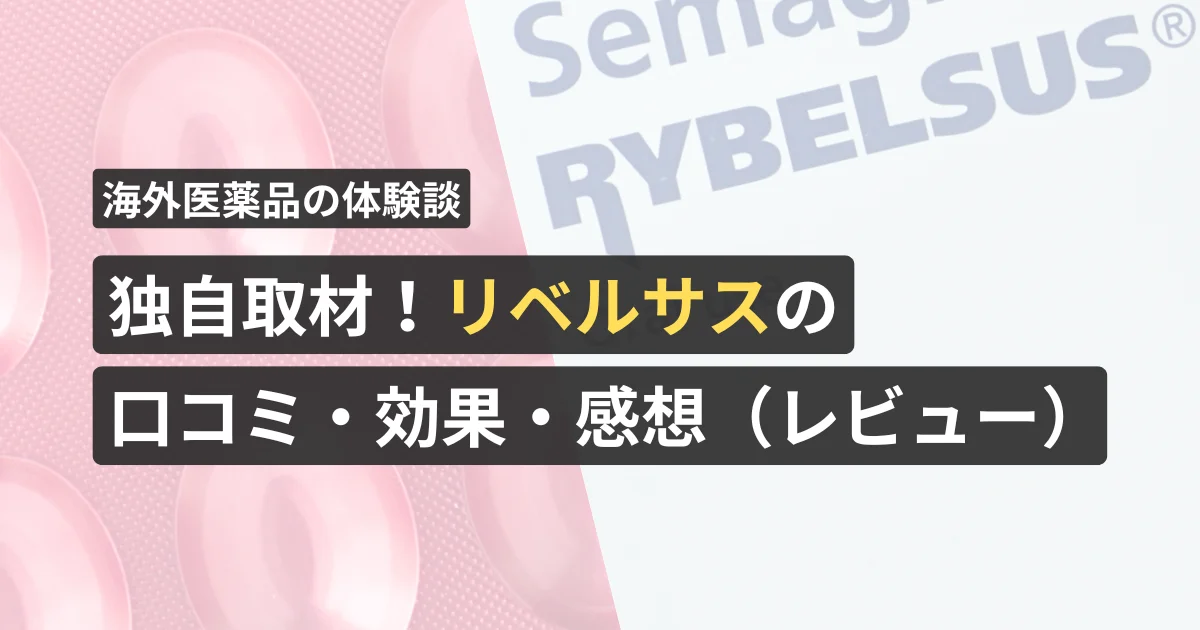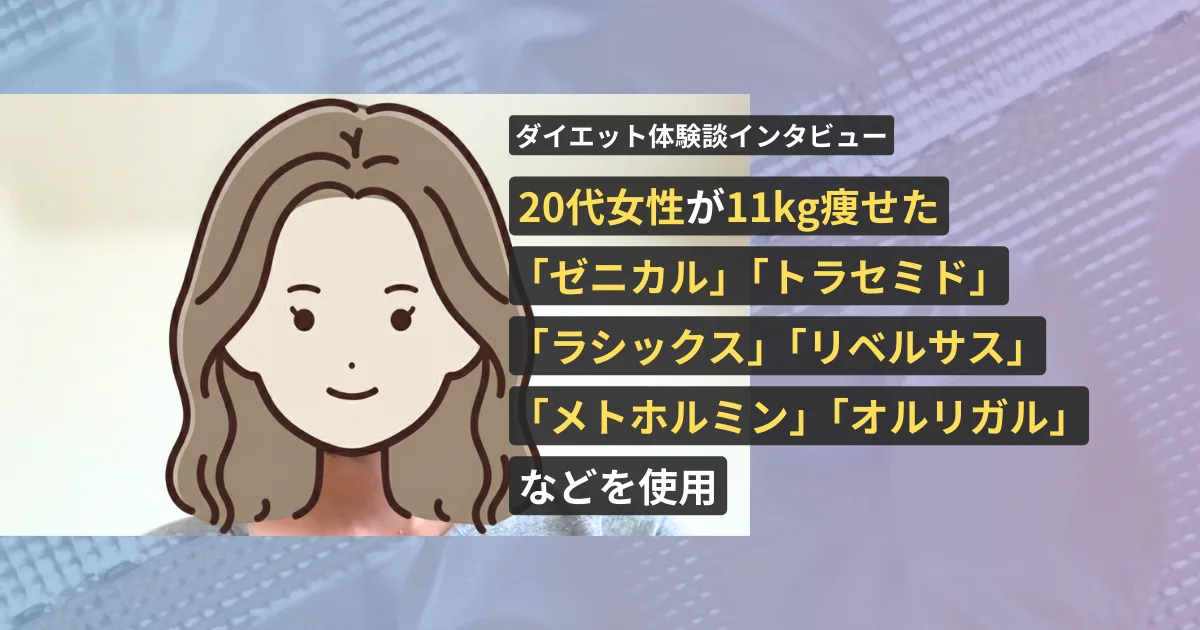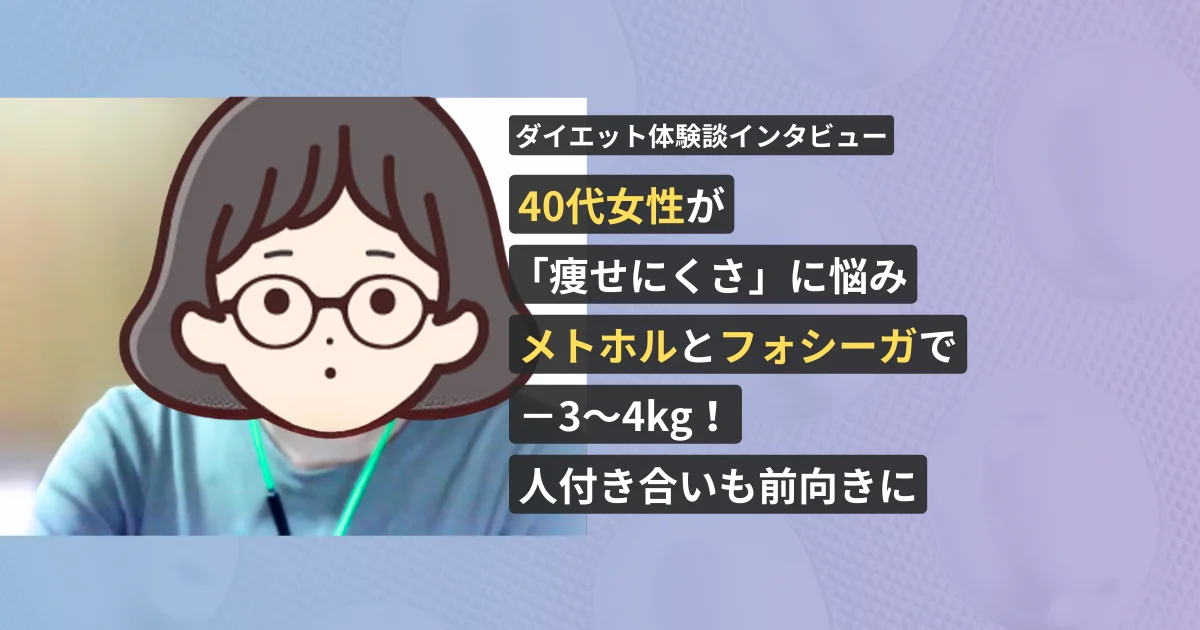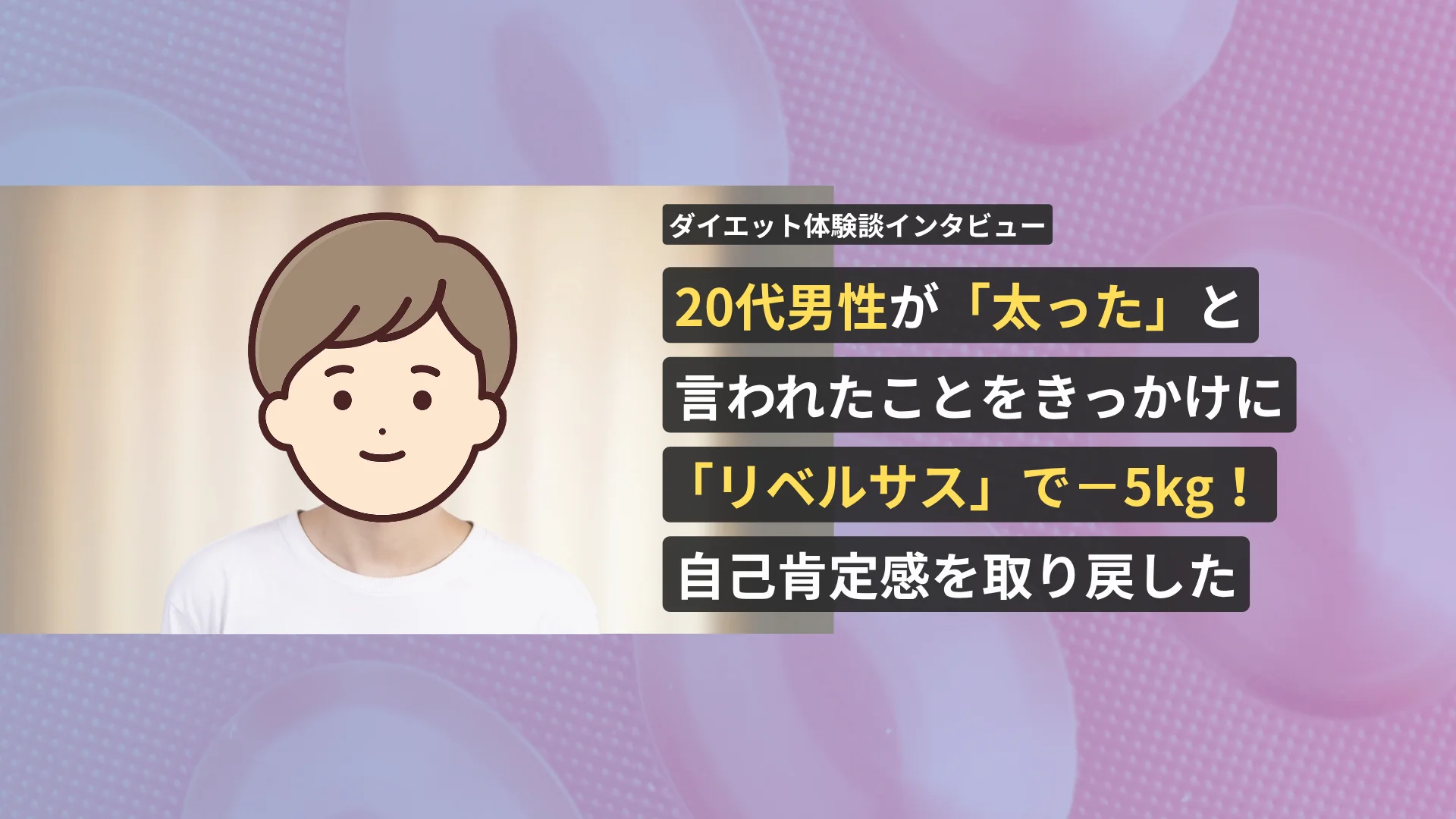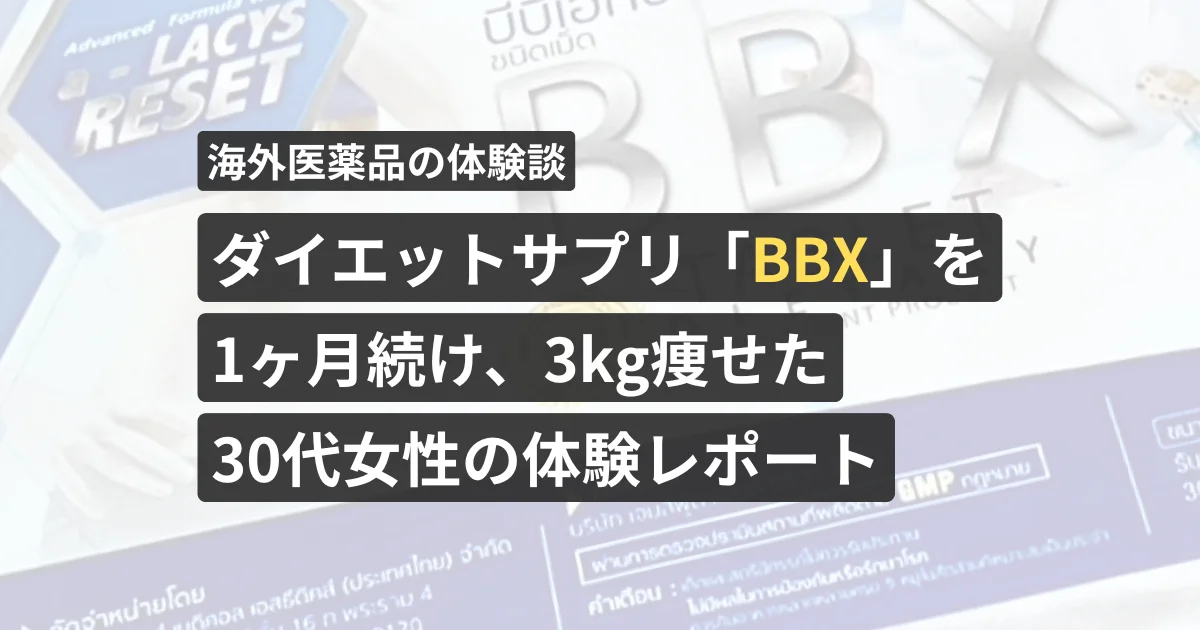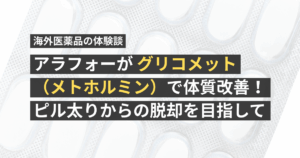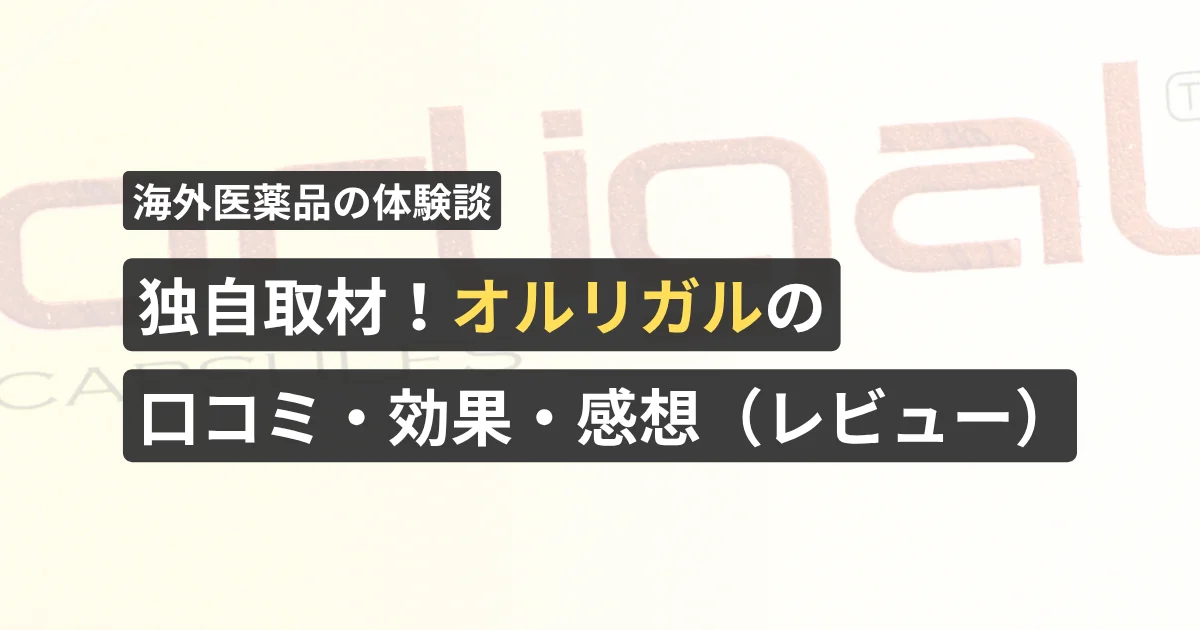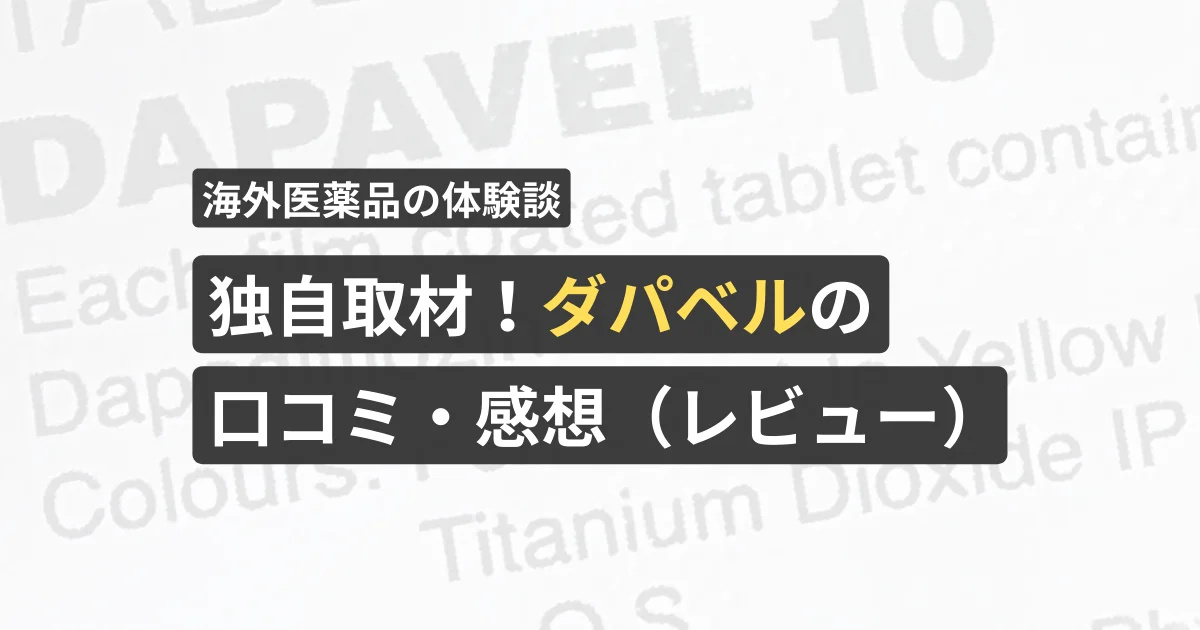豆乳には、大豆イソフラボンが豊富に含まれていて、美容や健康に良いというイメージはありますが、太りにくくなるとは、あまり聞かないかもしれません。
イシハラクリニックの医師、石原 新菜先生は「豆乳には植物性タンパク質が豊富で食物繊維も含まれる。食前に摂取することで食後の血糖値の上昇は緩やかになり、太りにくい体づくりができる。」と述べられています。
多くの栄養素が摂れて太りにくくなると考えられている豆乳について、今回、一卵性双子芸人でおなじみのザ・タッチの2人が徹底検証していきます。
この記事の要点は以下の通りです。
- 豆乳には大豆イソフラボン、植物性タンパク質、食物繊維などが豊富で、美容や健康に良い
- 満腹感の持続、血糖値上昇の抑制、脂肪蓄積の抑制など、太りにくい体づくりに役立つ
- 無調整豆乳が最適で、味に飽きる場合はきなこやココアでアレンジ可能
- 一卵性双子で「食前に豆乳を飲む/飲まない」を比較し、3日間の高カロリー食で検証
- 豆乳を飲んだ兄は体重増加が少なく、飲まなかった弟より太りにくい結果が出た
- 同じ条件下でも「食前に豆乳を飲むだけ」で差が生じることが確認された
- 臨床試験でも牛乳に比べて豆乳の方が腹囲減少効果が見られている
- 満腹ホルモンGLP-1の分泌増加やインスリン感受性改善など代謝への良い影響が確認
- 忙しい人でも取り入れやすく、長期的に続けることでより高い効果が期待できる
本記事では、『巷のウワサ大検証!実際どうなの会』の“食前に豆乳を飲むと太らない?”を実際に視聴した、以下の医療系国家資格を有する専門家が番組視聴レポートをお届けします。
 Kana
Kana看護師資格を有し、HCU、呼吸器内科·外科、整形外科などの多様な現場で経験を積んでまいりました。その中でも緩和ケアに携わってきた経験を強みとしています。
また、本記事の内容については、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。



看護師資格を有し、総合病院で勤務。退職後、出版社に勤務し、医学誌の編集も担当しておりました。
豆乳の栄養素とその効果
豆乳の栄養素と効果は次の通りです。
| 植物性タンパク質 | 動物性よりも脂質が少なく、カロリー過多になりにくい |
|---|---|
| 食物繊維 | 腸内環境の改善、血糖値の安定化 |
| 大豆イソフラボン | 更年期症状の軽減、骨粗しょう症の予防、脂質代謝改善 |
| サポニン | 抗酸化作用、免疫力向上、血流改善、肥満予防 |
| ビタミンB群 | エネルギー生産、神経・血液・皮膚の健康維持 |
| ビタミンE | 抗酸化作用、血流改善作用、動脈硬化予防 |
| カリウム | むくみ予防、神経・筋肉の働きをサポート |
| マグネシウム | 骨や筋肉・神経・心血管系の健康維持 |
| レシチン | 脂肪代謝、細胞・神経の健康維持 など |
豆乳に含まれる植物性タンパク質、食物繊維、サポニン、イソフラボンなどの成分は、満腹感の持続や血糖値の安定、脂肪蓄積の抑制などの効果があり、太りにくくなる効果が期待できると分かっています。
番組内ではこのほかにもビタミンB群、ビタミンE、カリウム、マグネシウム、レシチンなども太りにくくなる要因の1つになると紹介されていました。



植物性タンパク質は大豆タンパクともいわれるものです。
痩せやすい体を作る場合、ある程度のタンパク質接種が必要となります。
大豆の33%を占めるタンパク質は、動物性食品に比べても低カロリーで基礎代謝を活発にする機能があるため、太りにくい体を作るのに役立つと考えられています。
参考:
大豆たんぱくの力(肥満を予防・動脈硬化防止への期待): 豆乳の栄養成分|日本豆乳協会
豆乳で太る?太らない? 徹底検証!
番組内では一卵性双生児の芸人 ザ・タッチが食前に豆乳を飲む、豆乳を飲まないに分かれて体重差を比べていきました。
検証方法として
- 3日間実施
- 兄たくやが食前に豆乳を飲用、弟かずやは豆乳を飲まずに生活する
- 食前に豆乳200ml(小さなパックと同じ量)を飲む
- 食事は、平均カロリー以上を摂取する
- 消費カロリーもできるだけ同じにするため、同じ部屋で同じことをして過ごしてもらう
という同じ条件下のもと実施しました。
また、豆乳にはさまざまな種類がありますが、番組内では砂糖などが使われていない無調整豆乳を使用しています。
検証前の体重測定
検証前のザ・タッチ兄弟の体重は同じです!
- 豆乳あり → 兄たくや:開始前体重 75.2kg
- 豆乳なし → 弟かずや:開始前体重 75.2kg
1日目
- 朝食:かつ丼
- 昼食:カルボナーラ
- 夕食:すき焼き
約 2,800 kcal / 日 + 300 kcal(豆乳分)
- 兄たくや(豆乳あり):体重 75.5kg(初日体重+0.3kg)
- 弟かずや(豆乳なし):体重 75.6kg(初日体重+0.4kg)
2日目
- 朝食:牛丼
- 昼食:オムライス
- 夕食:ステーキ定食
約 2,700 kcal / 日 + 300 kcal(豆乳分)
- 兄たくや(豆乳あり):体重 75.3kg(初日体重+0.1kg)
- 弟かずや(豆乳なし):体重 75.9kg(初日体重+0.7kg)
3日目
- 朝食:ピザ
- 昼食:ラーメン
- 夕食:カツカレー
約 2,530 kca / 日 + 300 kcal(豆乳分)
- 兄たくや(豆乳あり):体重 75.4kg(初日体重+0.2kg)
- 弟かずや(豆乳なし):体重 75.8kg(初日体重+0.6kg)
結果
食前に豆乳を飲んだ方が太りにくい‼
以上の結果になりました。
ちなみに空き時間は、ゲームをして過ごしていました。
今回は、高カロリーの食事+運動をせずに生活をしていたため、多少の体重増加はありますが、それでも豆乳を飲んでいる人は太りにくいという結果になりました。
「豆乳を飲むと太りにくい」は科学的にも結論付けられていた!
最近の研究において、豆乳を飲むと太りにくいというのは科学的にも証明されています。
例えば「豆乳と牛乳を比べたクロスオーバー無作為化臨床試験」によると、毎日豆乳と牛乳を1杯飲んだそれぞれのグループの腹囲を比較すると、豆乳を飲んだグループでは明らかな腹囲現象が見られました。
ほかにも、満腹ホルモン(GLP-1)の分泌が約11%増加して食欲が抑制されたり、食後血糖上昇の抑制やインスリン感受性の向上(※)といった代謝改善作用も見られました。



※「インスリン感受性の向上」について補足です。
インスリン感受性(筋肉のブドウ糖を取り込む力)が高まり、ブドウ糖の取り込みが促進されるため、血糖を上げにくくします。
参考:
運動療法 – レジスタンストレーニング編(PDF)|神戸市立医療センター中央市民病院
科学的にも、『巷のウワサ大検証!実際どうなの会』で実証された豆乳のパワー、ぜひ一度試してみたいものですね。
種類別!豆乳の違い
今回の検証では無調整豆乳が使われていました。
しかし、豆乳の種類やその効果については十分理解できていない方もいるかもしれません。
豆乳の種類と効果は次の通りです。
| 種類 | 特徴 | カロリー (100g当たり) |
|---|---|---|
| 無調整豆乳 | 原材料の大豆のみで作られている。甘味なし | 43 kcal |
| 調整豆乳 | 飲みやすくするために砂糖などを使って甘さを調整している | 61 kcal |
| 豆乳飲料 | 果汁などを加えて味を変えている。糖質が最も高い | 57 kcal |
太りにくくするという目的で豆乳を飲むならば、無調整豆乳がベストな選択肢となります。
もしも、豆乳独特の香りや味が苦手という場合には、無調整豆乳にきなこや黒ゴマ、ココアなどを入れて自分で調整すると良いでしょう。
番組内でもきなこやココア、抹茶、黒ゴマを入れて味を変えて無理なく飲むことを勧めていました。
まとめ
今回は、3日間のみの検証ですが、あれだけの高カロリーな食事をして、やったことは食前に豆乳を飲むだけ。
それなのに初日体重から+0.2kgで終わるのはすごいですね。



大豆タンパク質は体内での吸収・分解に時間がかかり満腹感を得やすいとされています。
そのため、食事の前に豆乳を飲むことで、食事摂取量の減少にもつながります。
参考:
大豆たんぱくの力(肥満を予防・動脈硬化防止への期待): 豆乳の栄養成分|日本豆乳協会
この結果に出演者からは「3日間でこの結果だから、1か月とか続けたらどうなるのか!」というコメントもありました。
確かに、長期間続けるとさらに高い効果が期待できるかもしれません。
豆乳の味に飽きてしまいそうですが、アレンジレシピで味変しながら続けていけそうですね。
食前に豆乳を飲むだけなので、「忙しくてダイエットや健康に時間をかけられない。」という方にピッタリな方法ですね。
豆乳が苦手ではない方は試してみてはいかがでしょうか?