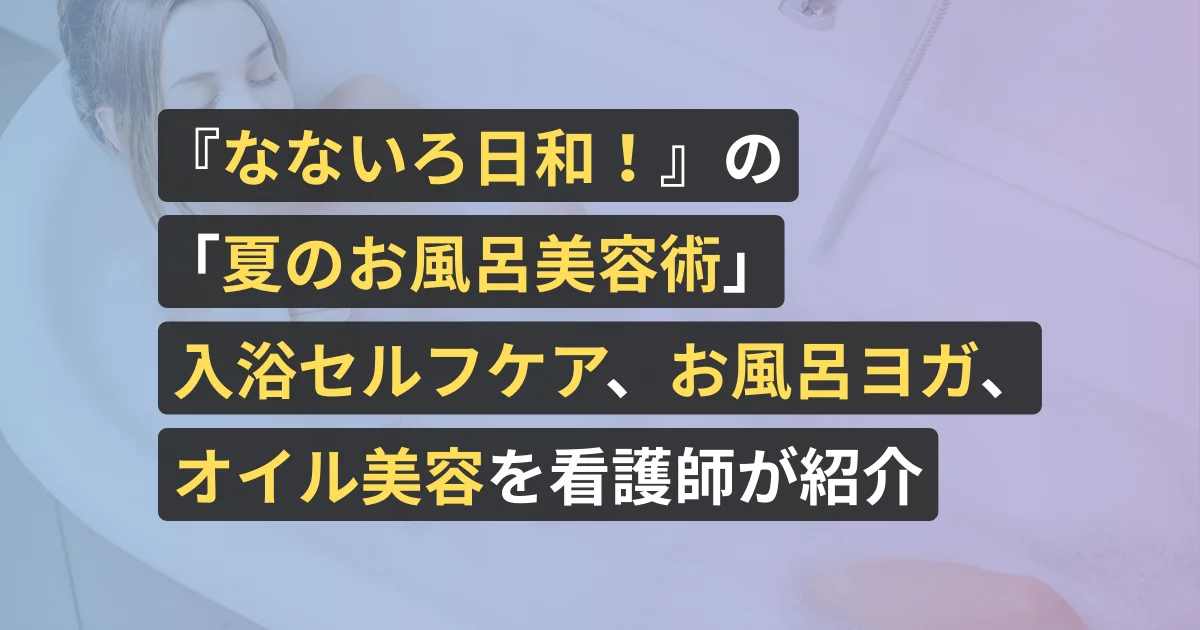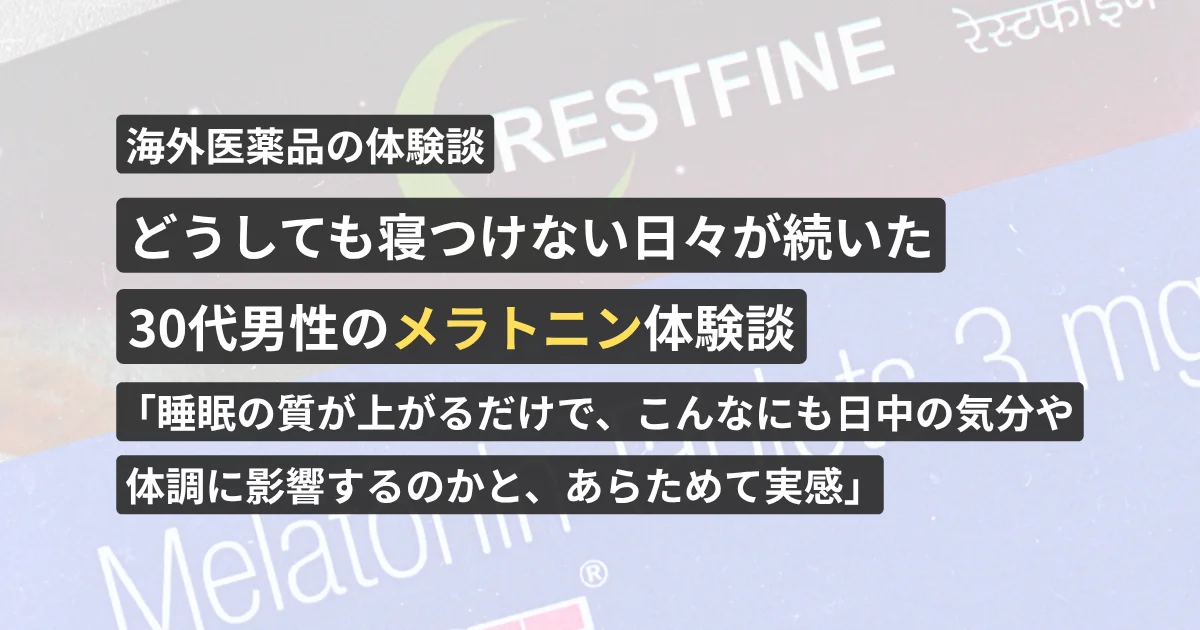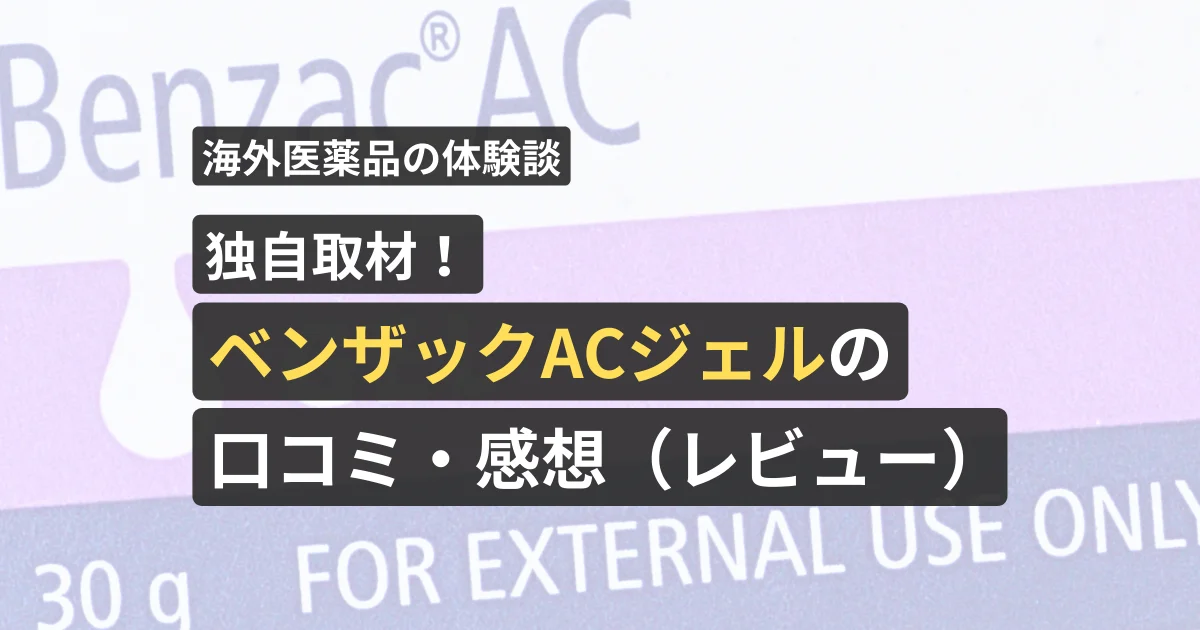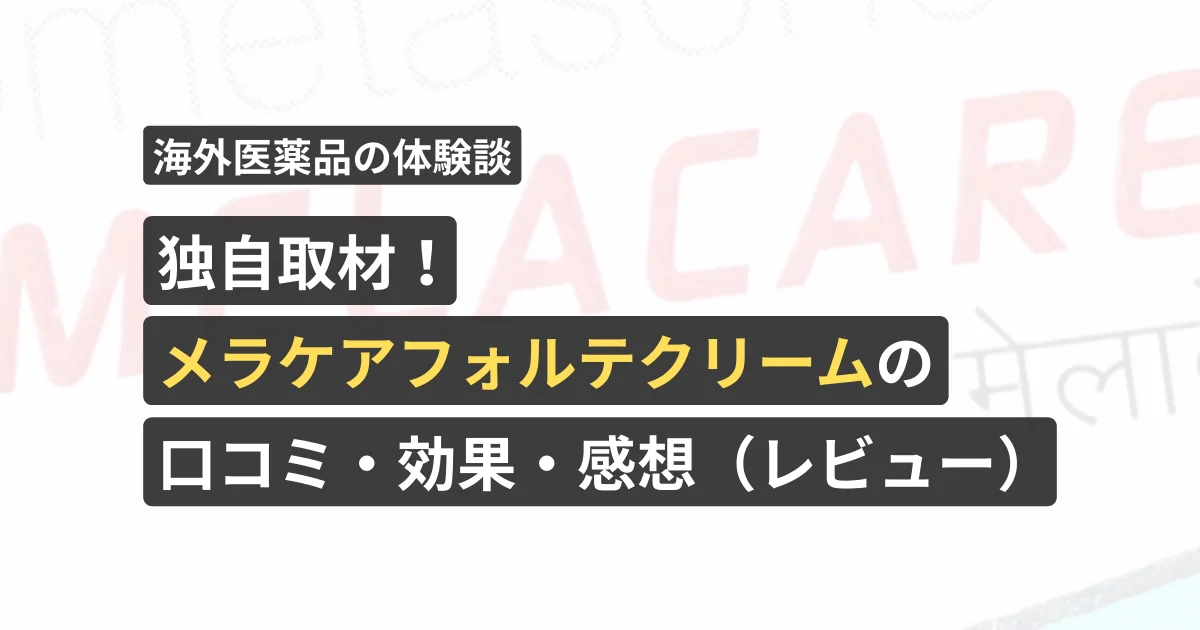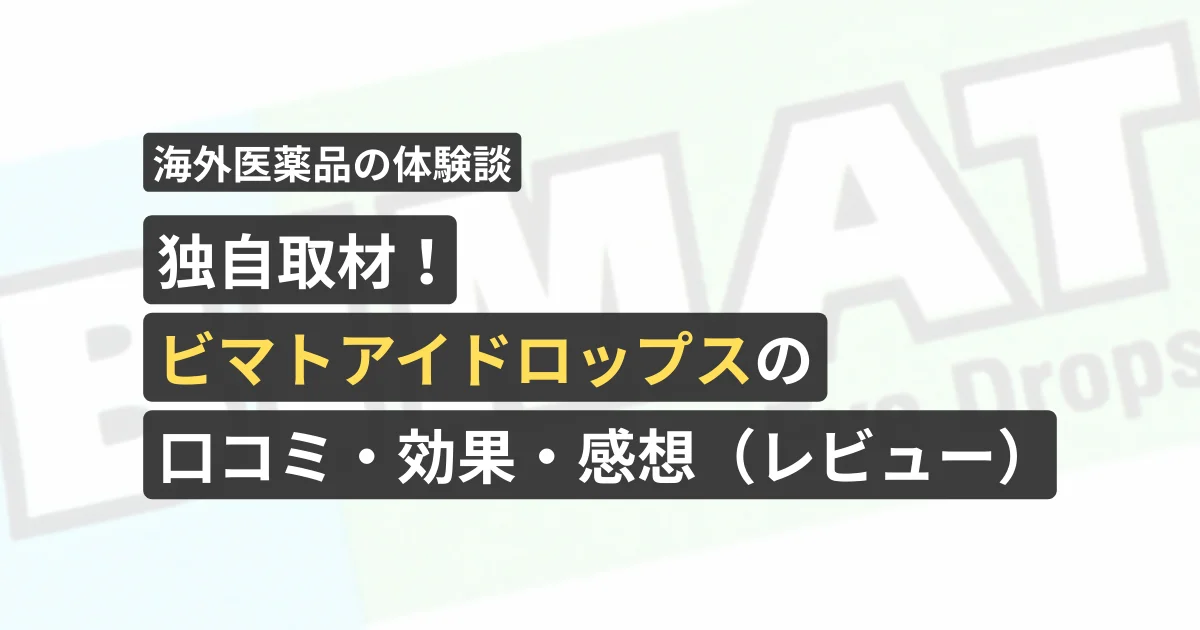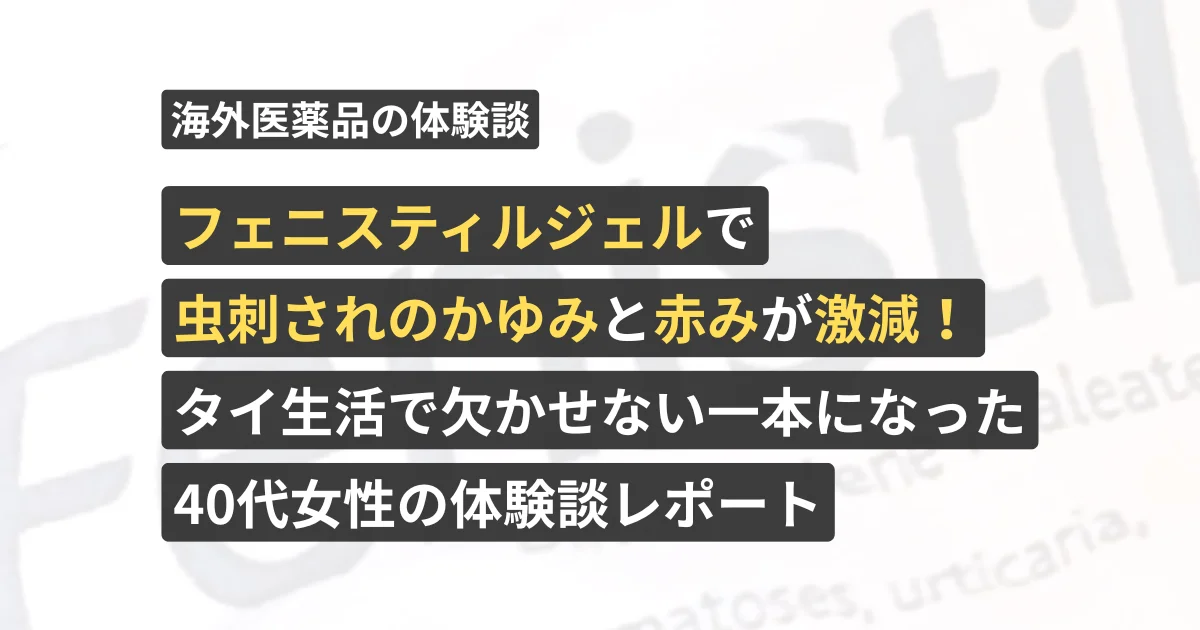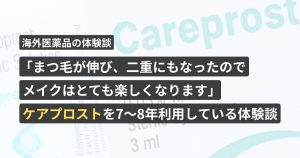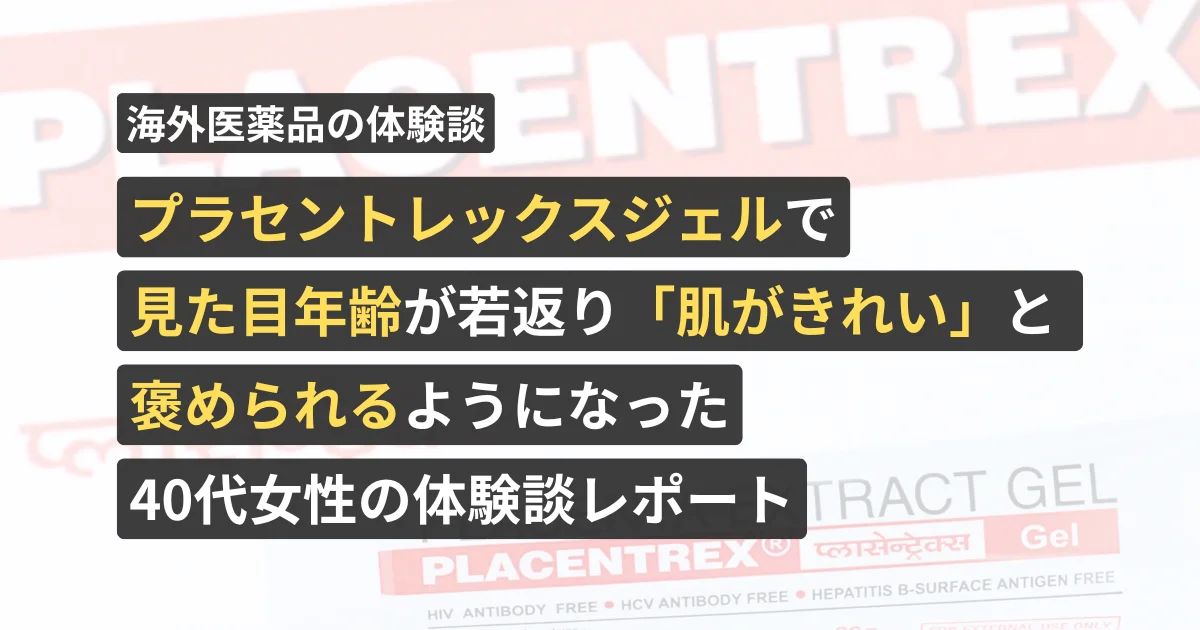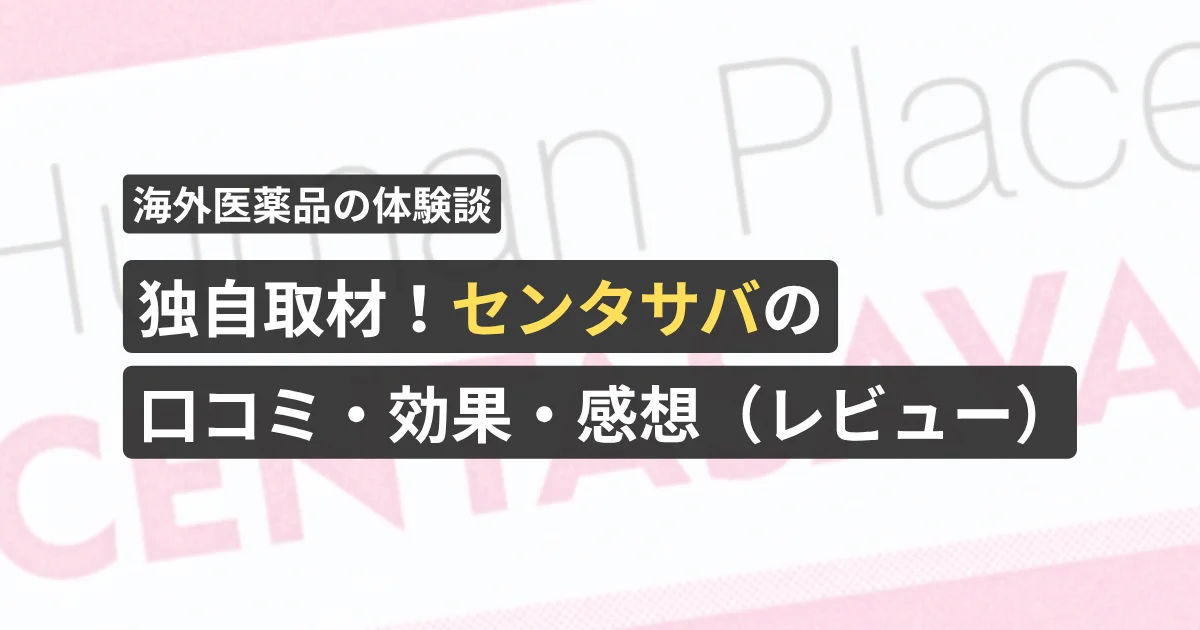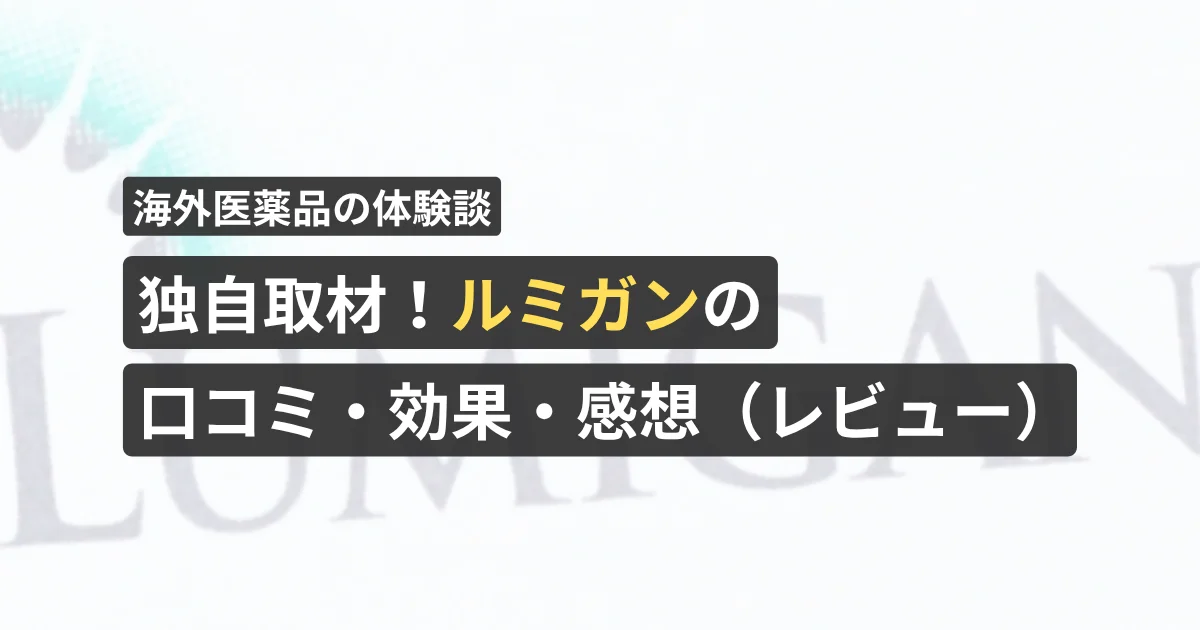暑い夏、お風呂に浸かることを疎かにしていませんか?
夏にお風呂に浸かることは美容面でメリットが多いのです。
BSテレ東『なないろ日和!』で2025年8月22日に放送された「夏のお風呂美容術」についてレポートします。
また、3人の美容のプロから聞いたお風呂で行える「入浴セルフケア」「お風呂ヨガ」「オイル美容」についても説明していきます。
この記事の要点は以下の通りです。
- 冷房や冷たい飲み物で自律神経が乱れ、血行不良や乾燥・むくみを招くため、湯船に浸かることが大切
- 夏の最適な入浴は38〜39度、10〜15分程度。炭酸系入浴剤で血流促進も効果的
- 入浴後は保湿を忘れず、むくみ改善セルフケアで顔・脚を整える
- ヨガは温熱・水圧・浮力の効果で血流促進・老廃物流し・体の負担軽減につながる
- 簡単な上半身・下半身ヨガを取り入れることで心身ともにリラックスできる
- 顔やふくらはぎのむくみ解消マッサージも浴中に行うと効果的
- 夏は紫外線や冷房で肌の角質層が乱れ、乾燥・ごわつきやすいためオイル美容が有効
- オイル入り石鹸・入浴剤で洗浄&保湿し、角質ケアタオルでターンオーバーを助ける
- 頭皮は紫外線でダメージを受けやすく、炭酸ヘッドスパなどで血流促進&リラックスを
本記事では、2025年8月22日に放送された「なないろ日和!」を実際に視聴した看護師が番組視聴レポートをお届けします。
 Akane
Akane看護士資格を有し、療養型病院や急性期総合病院(呼吸器・泌尿器)、特別養護老人ホームで10年以上勤務。認定音楽療法士の資格も取得しました。
また、本記事の内容については、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。



看護師資格を有し、総合病院で勤務。退職後、出版社に勤務し、医学誌の編集も担当しておりました。
おすすめ記事
おすすめ入浴方法と簡単セルフケアを紹介
お風呂で行える簡単なセルフケアについて、番組では皮膚科医錦糸町皮膚科内科クリニック院長 田尻 友里恵 先生のお話を聞きました。
夏にお風呂に浸かった方がいい理由
暑い夏こそ、シャワーで済ませるのではなく、お風呂に浸り、疲れをとることが大切と言われています。
理由は以下のようなものが挙げられます。
- 冷房、冷たい飲み物の摂取で深部体温が下がり、自律神経が乱れがち
- 自律神経の乱れで血行不足、また紫外線、汗による蒸発で、エアコンの影響で肌も乾燥している
- 紫外線の影響でリンパ節の多い顔に老廃物がたまり、むくみが起きやすい
- 暑さで運動不足のため、足も血流不足が起き、むくみが起きやすい
暑い夏は肌や体に思っている以上に負担がかかっているため、夏でもお風呂に入り疲れをとることが大切です。
夏おすすめの入浴方法
夏の入浴温度は38度〜39度、入浴時間は10〜15分でじんわり汗をかく程度が最適と言われています。
また、入浴温度が低めであるため、炭酸系の入浴剤を入れることで血流がアップするのです。
お風呂は思っている以上に汗もかくため、入浴後に保湿することも大切です。
むくみ解消!夏おすすめの簡単セルフケア
顔まわりのむくみ改善方法
- 手のひらを額にあて、耳元へ動かす
- 手のひらを頬骨 → 耳元へ動かす
- 手のひらを頬骨 → 顎の下
- 手のひらを顎の下 → 耳元
- 手のひらを耳の付け根 → 鎖骨
以上を無理のない範囲で5回繰り返しましょう。
ふくらはぎのむくみ改善方法
- 膝裏を両手でつかみ3~6回もみほぐす
- 足首を両手でつかみ数回にわけて膝裏まで流す
お風呂でヨガは効率的!おすすめヨガを紹介
お風呂で行うヨガについて、番組内ではヨガ・ピラティス・インストラクターのKaoruさんから話を聞いています。
お風呂でヨガを行うメリット
ヨガとは一般的にゆっくりと深呼吸をして筋肉を伸ばすことで、体の緊張を緩め、血流を良くする効果があると言われてます。ストレスも緩和され、心の健康にもつながるのです。
お風呂でヨガを行うことで、更なるメリットもあり、効果的です。
- 温熱効果により、血流が更にアップする
- 水圧効果により、全身の老廃物が流れやすい
- 浮力により体の負担が軽減される
お風呂で行う簡単ヨガ
上半身ヨガ
- 腕を交差させ、肩甲骨をつかみ体を丸める(丸めた状態で呼吸を整えよう)
- 両手を交差させて、両腕を立てて呼吸を整える(指先に意識を向ける)
- その手を頭の上に上げて、体を丸める
以上を無理のない範囲で5回繰り返しましょう。
腕が交差できない場合は手を合わせるだけで大丈夫です。
下半身ヨガ
- 両足を伸ばしてパタパタと動かす
- 片足を曲げて、前かがみになる
- 片足を持ち上げ呼吸しながら足首を回す
浮力があるため、シニアの方にも取り入れやすい運動です。
無理のない範囲で行いましょう。
お風呂は密室で人の目も気になりません。深呼吸を意識しやすく、自分だけの世界に入り込めるため、おすすめです。
夏は肌が乾燥しがち!お風呂時間でオイル美容
お風呂で行うオイル美容について、睡眠改善インストラクター・温泉入浴指導員・公認心理士である お風呂の専門家小林麻利子さんからお話を聞きました。
夏の乾燥した肌にオイル美容が効果的な理由
肌の表面は角質層と呼ばれ、皮膚が何層も重なって構成されています。この角質層は、
- 紫外線や雑菌などの外的刺激から肌守るバリア機能
- 肌の水分を守る保湿機能
などがあります。
紫外線の多い夏は、角質層が乱れやすく、肌荒れを起こしやすいです。
そこで美容オイルを使うことで角質層を保護し、肌の潤いを保つことができると言われています。
暑い夏だからこそ、お風呂にしっかり浸かり、オイル美容を使いましょう。
お風呂で使うおすすめのオイル美容
番組内ではお風呂で使うおススメのオイル美容として以下の商品を紹介していました。
① オイル入り石鹸
| 商品名 | TSUKUYOMI TOFUlly おからハーバルソープ 2,970円(税込) |
| 効能 | 米ヌカ油、ヤシ油が余分な皮脂や汚れのみを洗浄肌の内側の水分を整えてくれる。 |
② オイル入り入浴剤
| 商品名 | SLEEP STEP ミルクパウダー 297円(税込) |
| 効能 | オリーブオイル×ホホバオイル配合エプソムソルト(硫酸マグネシウム)+炭酸成分で血行促進、肌のバリア機能を整える。温度が低くても効果あり。 |
実際に入浴しているひとの割合は?
冬と夏で実際に入浴している人の割合を番組でアンケートをとっています。
① 冬の入浴スタイル
| しっかりお風呂に浸かる | 58.8% |
| 軽めにお風呂に浸かる | 8.3% |
| シャワーで済ます | 21.8% |
| その日の気分 | 10.2% |
② 夏の入浴スタイル
| しっかりお風呂に浸かる | 23.7% |
| 軽めにお風呂に浸かる | 13.6% |
| シャワーで済ます | 54.1% |
| その日の気分 | 7.8% |
しっかりとお風呂に浸かる人の割合が冬は58.8%であるのに対し夏は23.7%と半分程度であることが分かります。
入浴は、副交感神経が優位になり、リラックス効果があります。
睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げないためにも、電気を消し、とにかくリラックスすることが大切です。
※医薬品としてのメラトニンを服用された30代男性の体験談レポート、睡眠負債の記事もございますので、あわせてご覧ください。
お風呂上りの頭皮ケア紹介
夏は紫外線で頭皮も傷みます。入浴後は頭皮ケアも行いましょう。番組内では以下の商品が紹介されていました。
| 商品名 | SLEEP STEP 炭酸ヘッドスパ 1,700円(税込) |
| 効能 | パチパチはじける高濃度炭酸で、頭皮にアプローチ。 頭皮の血流が良くなるため、副交感神経が優位になりリラックスし睡眠へ促します。 |
美容オイルが浸透しない皮膚には?おすすめのケア商品紹介
夏の紫外線で肌のターンオーバーは遅くなり、肌はごわついていきます。
そのため美容オイルも肌に浸透しづらくなるんです。皮膚の角質を落とすケアも行いましょう。
| 商品名 | ループオーシャンタオル |
| 効能 | ツイストループ繊維が軽くこするだけで、古い角質を絡めとります。 気になる踵や肘などやさしくなでることでツルツルの肌が目指せます。 |
夏のお風呂美容術まとめ
暑い夏は紫外線や、冷房の刺激などで肌や体には思っている以上に負担がかかっていると番組内でも解説していました。
お風呂にまずしっかり浸かること、そして本日紹介した「入浴セルフケア」「お風呂ヨガ」「オイル美容」を少しでも取り入れて、疲れをとりましょう。
そして肌の不調やむくみ改善、睡眠の質の向上につながるといいですね。
おすすめ記事