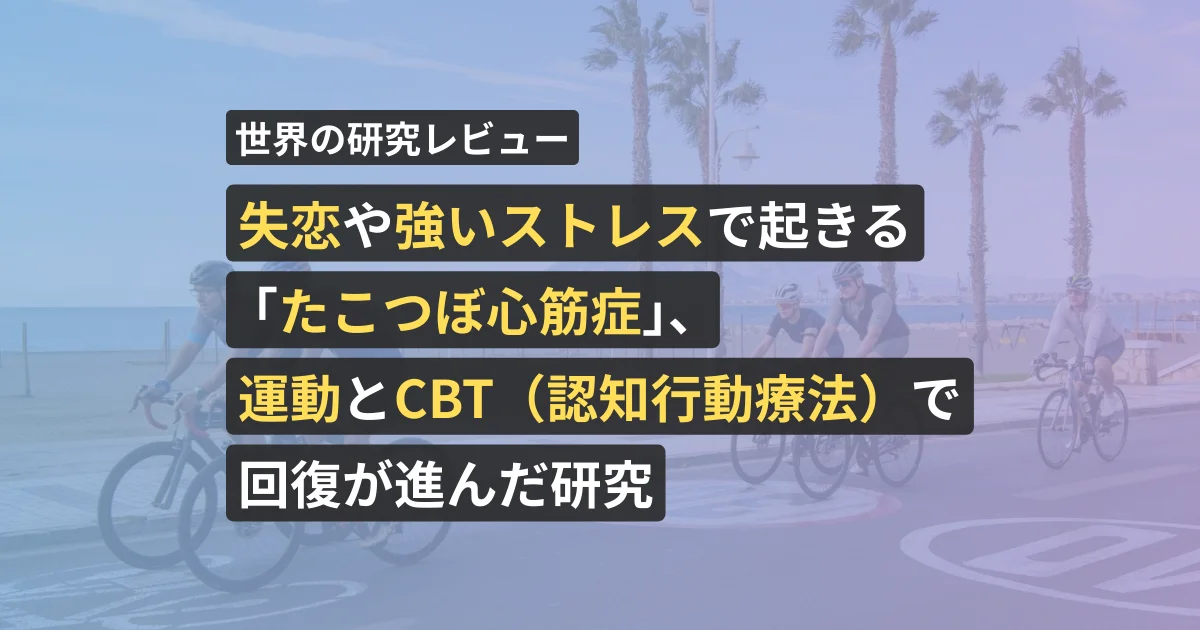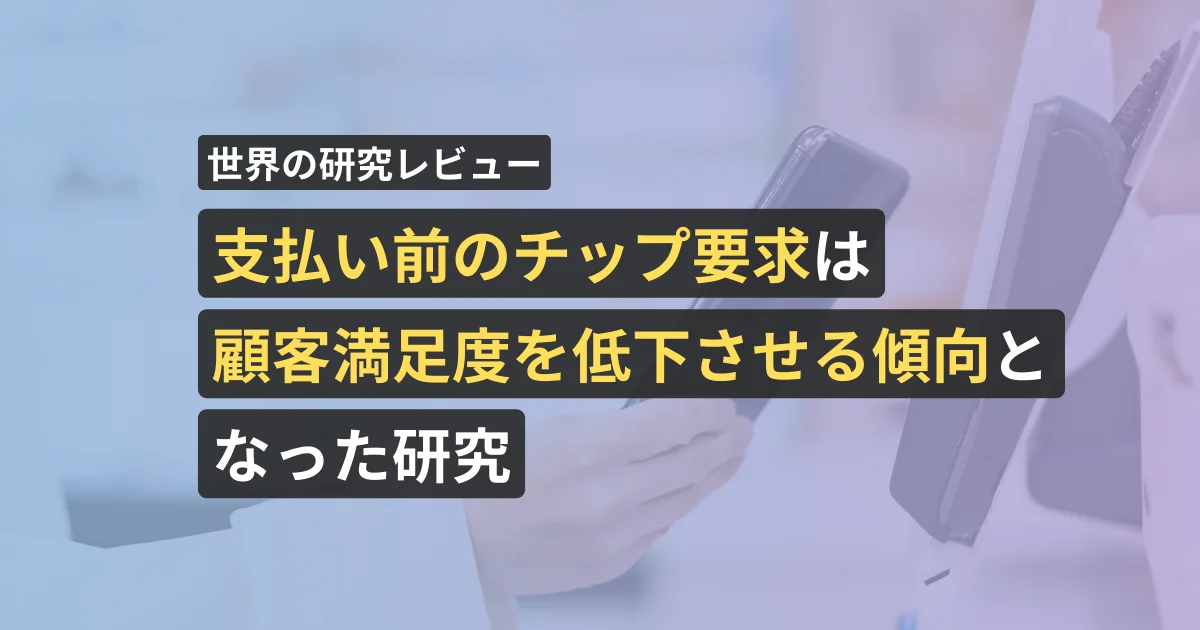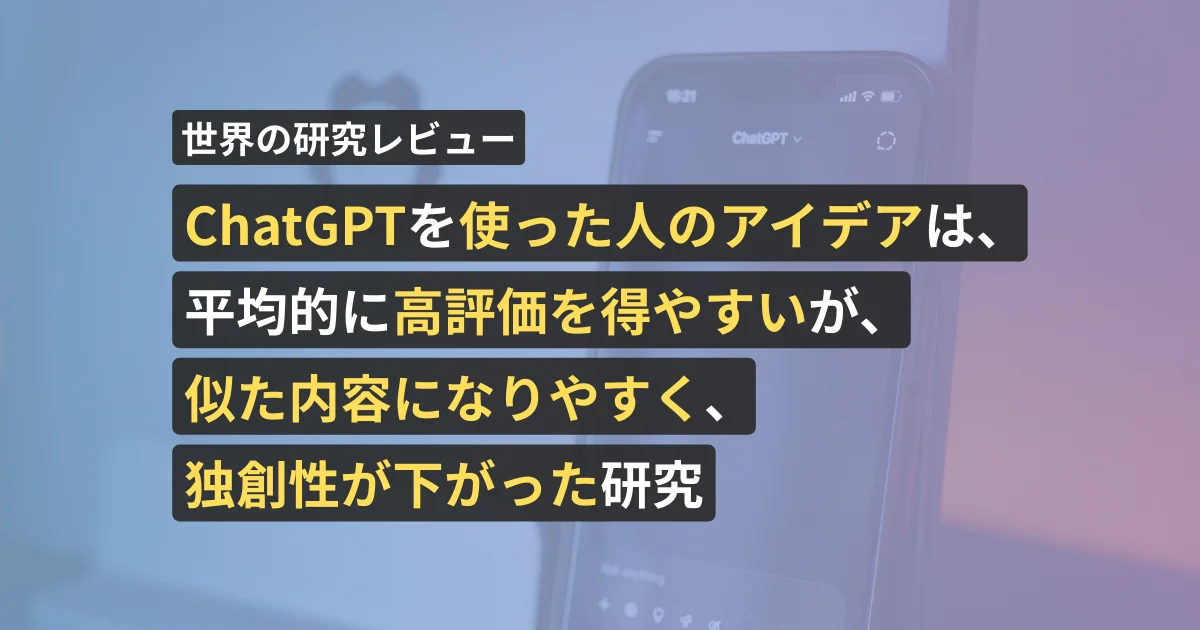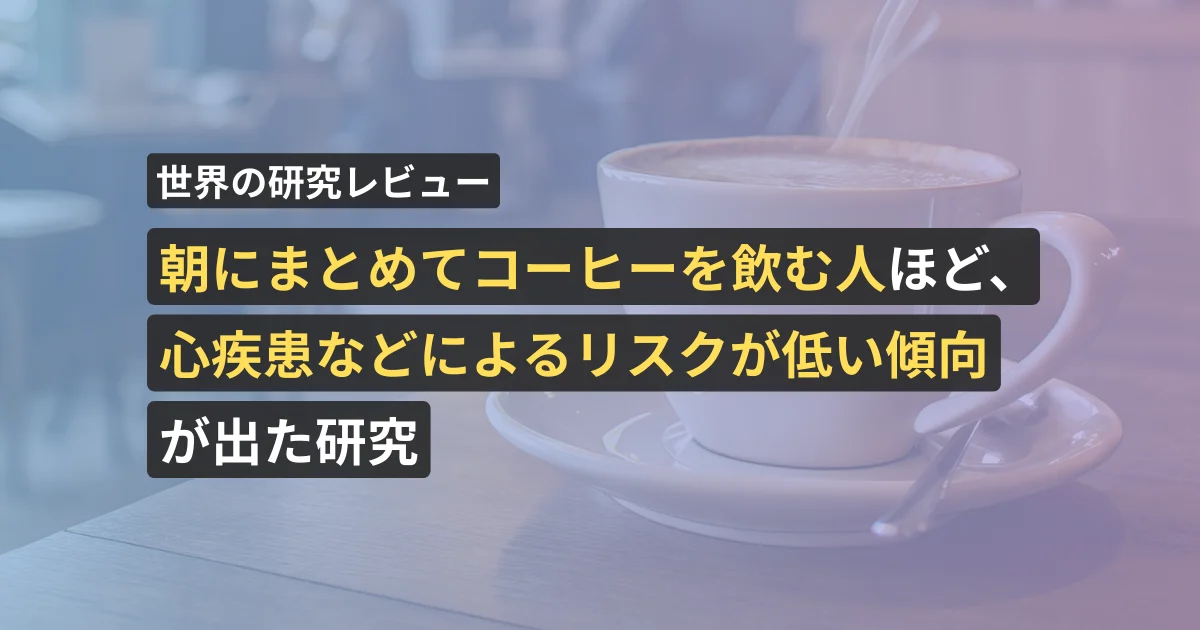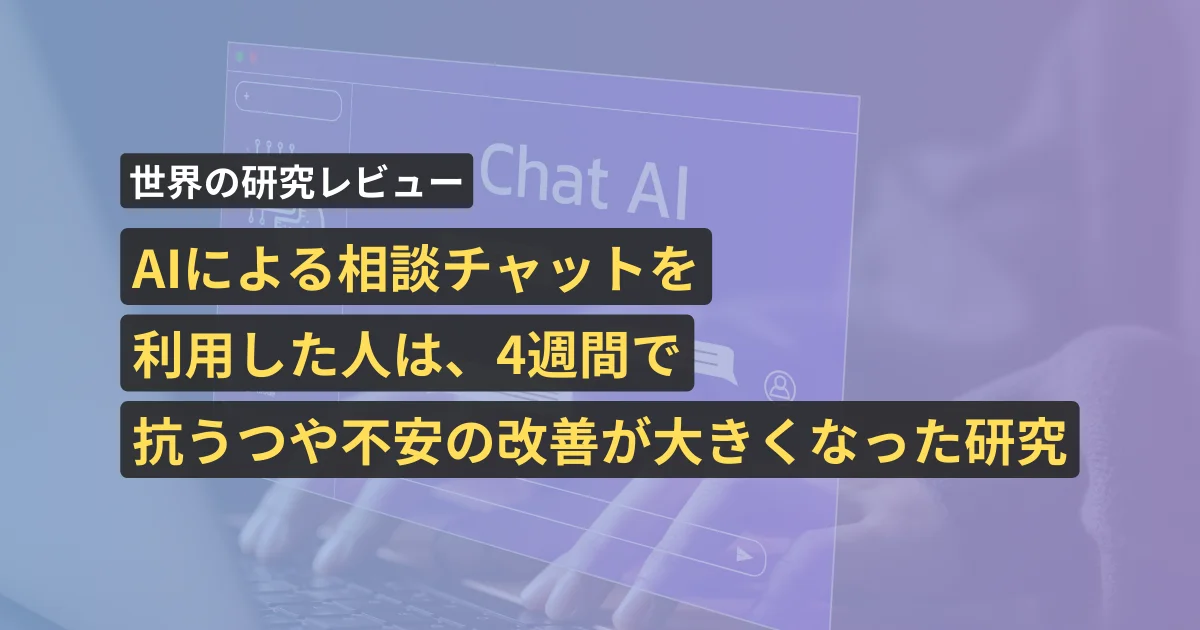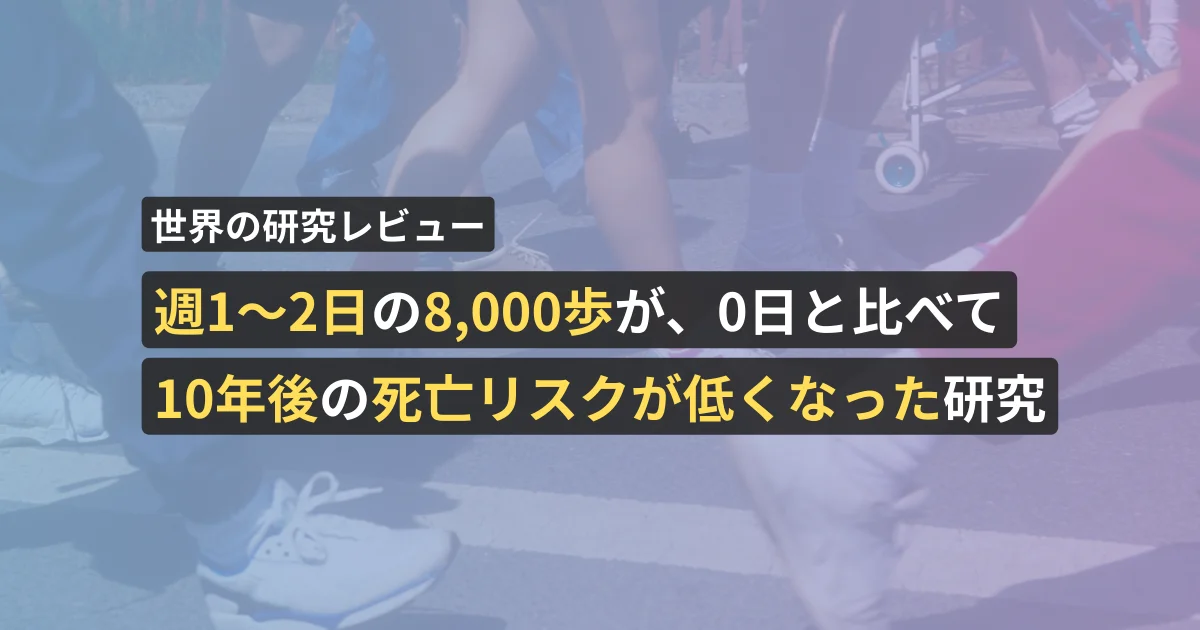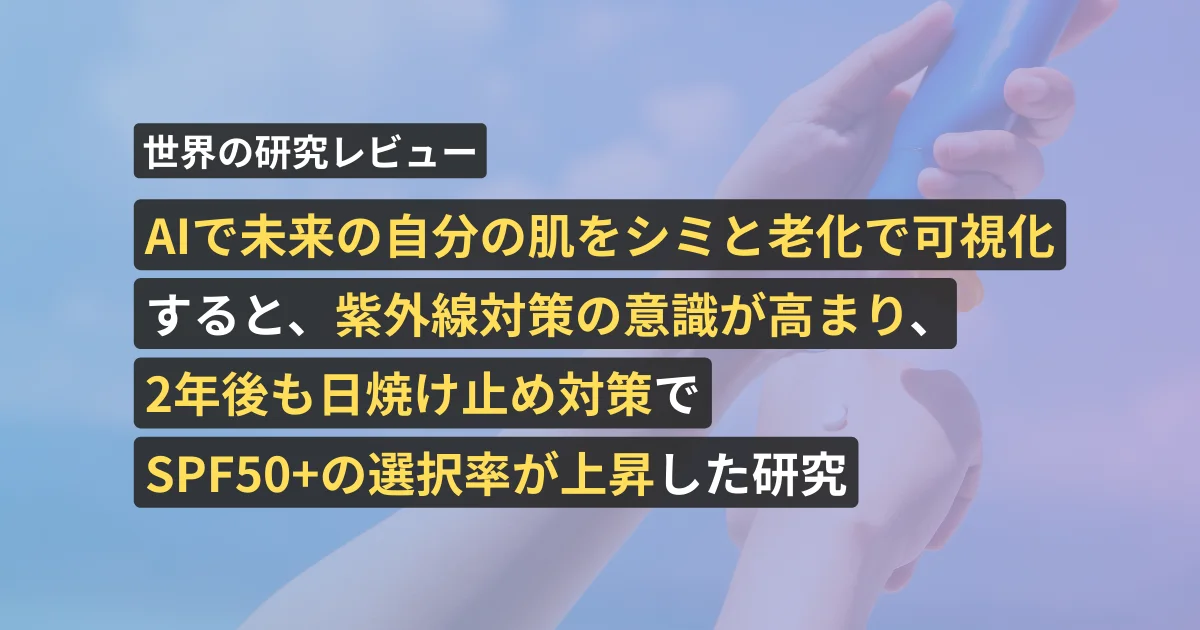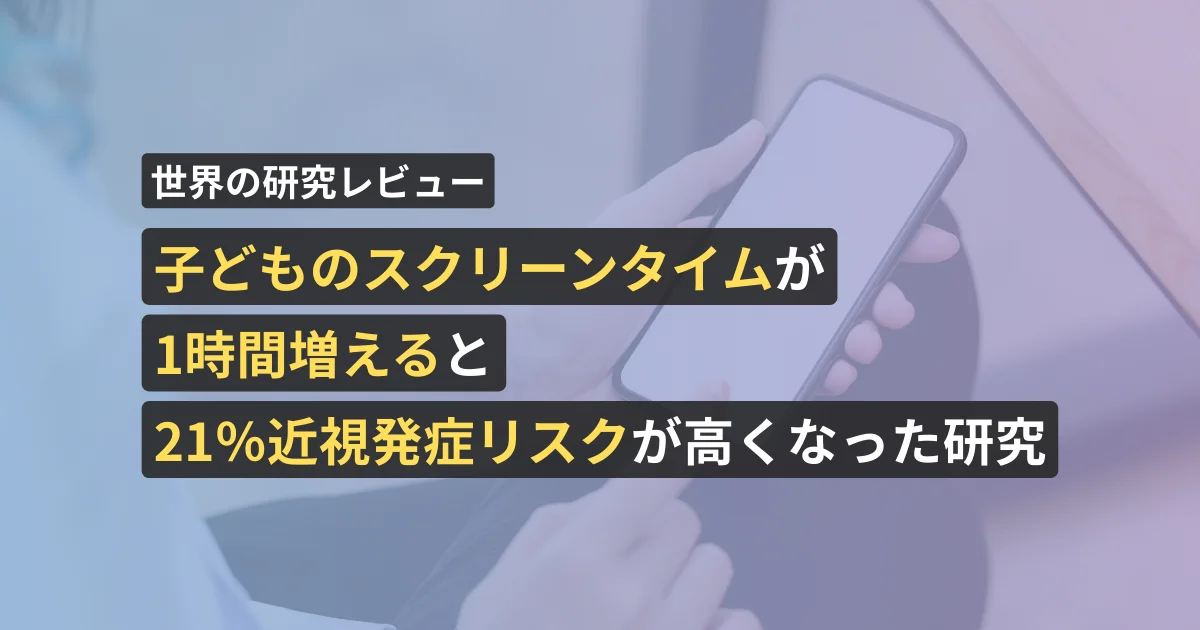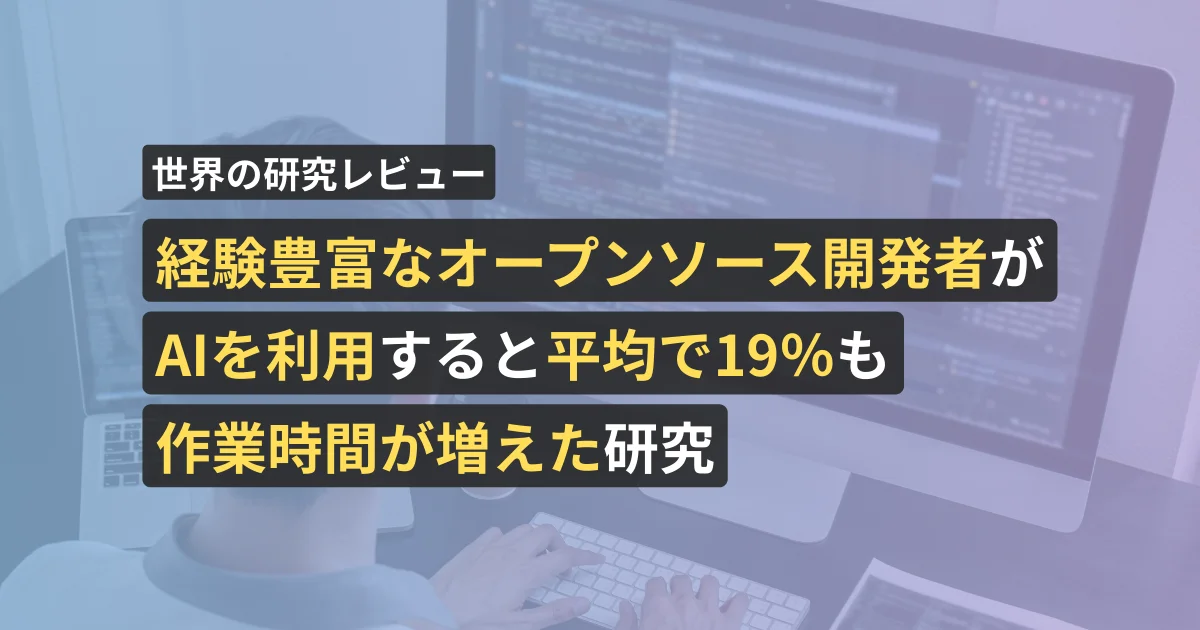心筋梗塞のような胸痛で搬送されても、血管が詰まっていないときに見つかるのが「たこつぼ心筋症(心臓の一時的な収縮障害)」です。主に中高年女性に多く、強いストレスが引き金となり一時的に心臓の働きが低下します。
最新のランダム化比較試験(BREAKOUT試験、対象76名)では、12週間の運動療法やCBT(認知行動療法)が体力や心臓のエネルギー代謝を改善する効果を示しました。規模は小さいものの、再発予防や生活の質の向上につながる可能性が示されています。
本記事では、たこつぼ心筋症の特徴と最新研究から分かった運動とCBTの効果を分かりやすく紹介します。
- Khan H, et al. Takotsubo syndrome: cognitive behavioural therapy, physical training, and brain function recovery in the BREAKOUT trial. European Heart Journal. Online ahead of print, 2025.
- University of Aberdeen / ESC Congress 2025 発表情報
(試験設定の概要と演題情報) - The Guardian「Exercise and therapy can mend a broken heart, study suggests」2025-08-30
(主要アウトカムの数値を報道)
本研究の要点は以下の通りです。
- 12週間の運動(ウォーキングなど)やCBTで、体力指標が改善しやすい傾向
- 6分歩行距離は +56〜71m、最大酸素摂取量(VO₂max)は +15〜18%の改善が報告されている
- 心臓のエネルギー代謝の回復傾向が画像検査で確認された
- ウォーキングなど息が弾む程度の運動を、必ず主治医と相談のうえで再開する
- 不安や不眠が強い場合は、CBTや心理相談窓口の利用を検討する
- 運動は週3回、20〜30分程度から無理なく開始する(治療計画は医師と調整)
- 試験規模は小さく、効果の大きさや再現性は今後の検証が必要
- 症状がぶり返すこともあるため、自己判断で運動強度を上げない
- 胸痛や息切れが悪化した場合はすぐ医療機関を受診する
なお、本記事の内容については、表現に不自然な点がないか、医学雑誌の編集にも携わっていた編集の専門家が確認済みです。
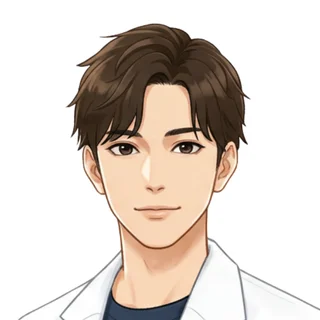 Touma
Touma編集プロダクションでの勤務経験があり、医療系出版社の月刊誌にて校正、校閲業務実績がございます。
おすすめ記事
研究の概要
イギリスの研究チームは、たこつぼ心筋症の回復期患者を対象に、運動療法またはCBTが症状や心機能の改善にどの程度寄与するかを、これまでで最大規模のランダム化比較試験で検討しました。
本研究は、患者の心臓機能、生活の質、心理的状態を評価し、介入の有効性を科学的に検証する初めての大規模試みです。速報は医学誌 European Heart Journal に掲載されています。
| いつ | 2025年8月、オンライン先行公開 |
|---|---|
| 誰が | アバディーン大学ほかの研究チーム(BREAKOUT試験) |
| 対象 | 主に女性76人、平均年齢66歳、タコツボ型心筋症発症後の回復期 |
| 方法 | 運動群:12週間の段階的リハビリ(自転車、スイミング、エアロビクスなど) CBT群:週1回、全12回の個別認知行動療法(CBT)セッション 対照群:標準的ケア |
| 評価項目 | 体力:6分間歩行距離(m)、最大酸素摂取量(VO₂max) 心臓のエネルギー代謝(代謝回復の指標) |
| 結果 | ・運動群とCBT群の両方で体力の向上が見られました。具体的には、6分間歩行距離が56〜71m増加し、VO₂maxが15〜18%向上 ・心臓の代謝回復も好ましい傾向を示し、回復期の患者における心機能の改善に関与している ・一方、標準ケア群では体力や代謝の改善はほとんど確認されなかった ・運動群とCBT群のいずれもが効果的であり、心理的支援が体力の改善に一定の影響を与える可能性が示唆された |
たこつぼ心筋症はなぜ長引くのか
たこつぼ心筋症は、強いストレスが引き金となって発症し、心臓のポンプ機能だけでなく、エネルギーの生成やその使い方にも影響を及ぼすと考えられています。そのため、ただ安静にして自然に回復を待つだけでは、体力が落ちたり、不安感が長引いたりすることが多いです。
運動療法を通じて筋力や持久力を回復させることと、CBTを用いて不安や回避行動を改善することを組み合わせることで、回復をサポートする効果があることが示されています。
本研究では、運動とCBTの両方を取り入れることで、症状の改善が期待できることが確認されました。
家でできる始め方(主治医にOKをもらってから)
心臓の回復やメンタルの安定をサポートするために、ウォーキングの始め方やCBTを受ける方法をお伝えします。初めて取り組む方や体調に不安がある方は、必ず主治医に相談してください。
ウォーキングの目安
会話ができるくらいのゆっくりしたペースで20〜30分を目安に行うのが理想です。また、週に3回程度、体調が良い日に行うのが基本で、坂道や負荷の大きい場所は避けて、無理のない範囲で行いましょう。
運動後には、息切れや胸の違和感、疲労感が残っていないか確認し、状況を記録しておくと体調管理に役立ちます。慣れてきたら、5分ずつ時間を延ばすなど、少しずつ負荷を増やすと続けやすくなります。
CBTを受けるには
心臓リハビリ外来の心理士や精神科・心療内科の臨床心理士、またはオンラインで提供されるプログラムを利用することができます。
面談やセッションを受ける際には、睡眠状況や不安の程度、日々の活動量などを記録しておくと、より具体的なアドバイスを受けやすくなります。
家庭でできる取り組みはあくまで補助的なものであり、症状に変化が出た場合は、すぐに医療機関に相談してください
今回の研究の限界と今後の課題
本研究は76人を対象に行われたため、結果を一般化するには限界があります。短期的な評価が主に行われており、長期的な再発や入院率の改善については示されていません。また、追跡期間や評価指標の詳細も十分ではありません。
今後は、参加者数を増やし、長期的な追跡研究が必要です。 しかし、これまで明確な有効策がなかった病気に対して、現実的で実践可能な治療や介入の選択肢が示されたことには大きな意義があります。特に、患者自身が取り組める生活習慣や運動療法の提案は、臨床応用の可能性を広げるものです。
たこつぼ心筋症に関するよくある質問
まとめ
12週間の運動療法とCBTを組み合わせることは、たこつぼ心筋症からの回復を、客観的なデータと主観的な体験の両面からサポートする可能性が考えられます。
たこつぼ心筋症は、強いストレス反応によって一時的に心臓の機能が低下する状態です。最近の研究では、適切なリハビリと心理的なサポートが回復に重要であるとされています。運動療法は心臓の機能を良くし、CBTは不安やストレスを減らすことが期待できます。
現時点では「これしかない」という治療法はありませんが、医師の許可を得た上で、無理のない範囲で運動と心のケアを並行して行うことが、回復に向けた良い一歩になるでしょう。
おすすめ記事